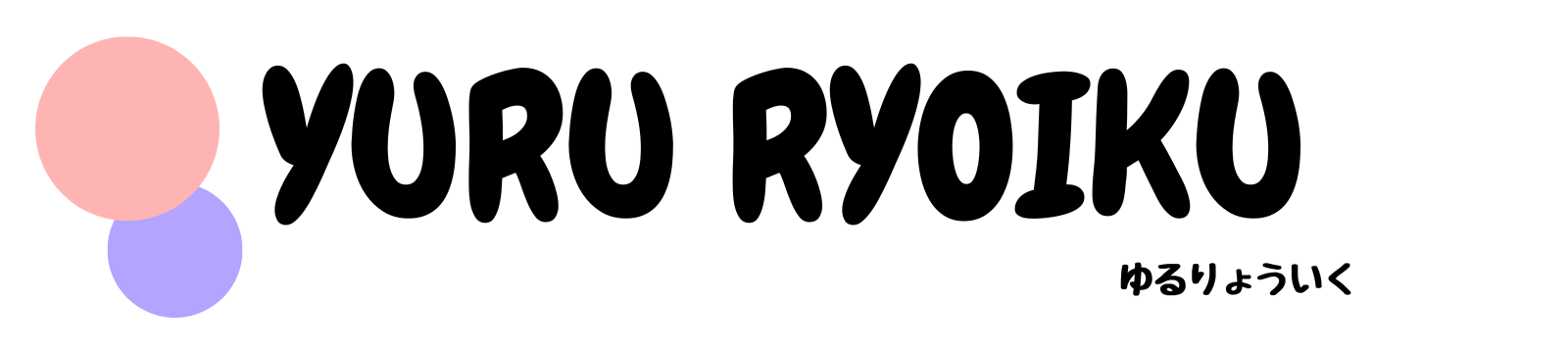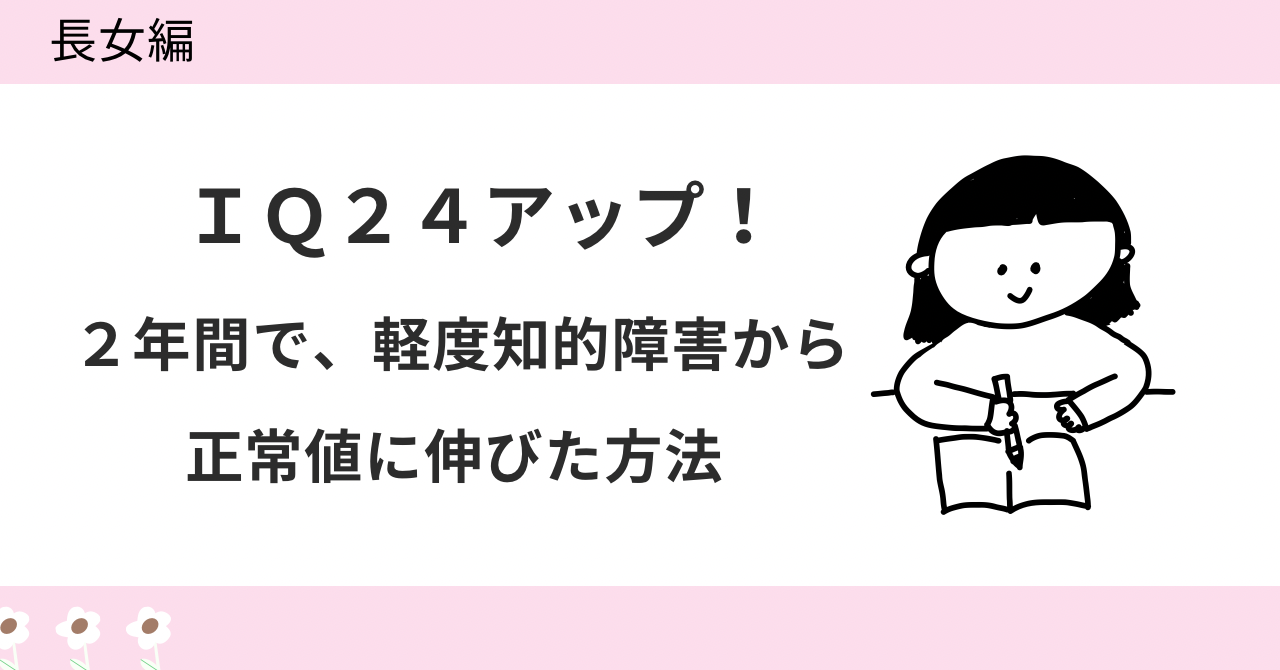こんにちは、ゆるママです。
3歳の発達検査で軽度知的障害と診断されてから5歳で正常値になるまでの2年間、娘と一緒に、できることを少しずつ積み重ねてきました。
「言葉さえ出れば、きっと伸びるはず」と思っていたけれど、実際には、単語が少しずつ出てきていた時期でも、
発達検査のIQは下がってしまっていて、すごくショックでした。
言葉を話せるようになるだけでは、IQは伸びない。
そう気づいたとき、改めて「理解力を育てるって大事だ」と思いました。
この記事では、発達検査のIQが2年で24伸びた娘との家庭学習について、私なりにやってよかったことをまとめています。
同じように悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。
家庭学習と日常生活の見直しで、理解力がぐんぐん伸びた
療育だけでは限界がある?家庭の関わりを強化
娘は、2歳のときは週4回の療育に通っていました。
しかし、1年後に受けた発達検査の結果は、数値が下がっていました。
 ゆるママ
ゆるママこれだけ通ったのに、どうして下がるの…
と、正直落ち込みました。
この経験から、療育だけでは、娘の成長に限界を感じ始めました。
そこで我が家では、家庭学習や日常での関わりを見直すことにしました。
- 療育を週1に減らす
- 外出や体験の時間を増やす
- 毎日の家庭学習を習慣にする
これまで療育中心だった生活を見直し、家庭での関わり・遊び・学習のバランスを重視するようにしました。
このシンプルな方針転換が、結果的に大きな変化につながっていきます。
家庭で取り組んだこと①|外の世界や習い事で「感じる力・考える力」を育てた
娘の療育を週1回に絞り、空いた時間はできるだけ外出や体験活動、そして習い事に使うようにしました。
知的好奇心や理解力を育てるために意識したのは、五感を使った“実体験”の積み重ねです。
我が家で取り入れた外の体験や活動
- 公園で自然に触れる
- 買い物で数や言葉に触れる
- 旅行で新しい景色や人との出会いを経験
このように、五感や実体験を通して「感じる→考える」力が育っていくことを実感しました。
公園で自然に触れる
草花・虫・天気など、季節の変化を感じる中で「観察力」や「語彙力」が育ちました。
スーパーやコンビニで買い物体験→ 数字・商品・会話など、生活に直結した言葉を自然に学べました。
実は、当時の娘は「キャベツ」や「大根」のような日常でよく目にする野菜の名前も、自分から言うことができませんでした。
絵本などを使えば指差しはできるのに、「これはなに?」と聞いても黙ったまま。
理解しているのに言葉として表現できないもどかしさに、私自身も悩んでいた時期です。



それでも買い物中、「キャベツあったね」「大根あったね」とぽつりとつぶやいた瞬間は、まるで心の扉が少し開いたように感じました。
小さな一歩が、すごく嬉しかったのを覚えています。
旅行や外食で初めての体験をする
知らない景色、人、食べ物に出会うことで、感情・言葉・記憶の幅が広がったと感じています。
習い事(スイミング)を始めた
スイミングは、娘にとって初めての集団の習い事でした。
私は、水が怖くて泣くのでは……というよりも、



初めての場所・初めての先生・初めてのルールの中で、何もできずに固まってしまうのではないかと、とても心配していました。
でも、いざ始めてみると、娘は驚くほど落ち着いていて、先生の話を静かに聞き、まわりの子をよく見て動こうとしていたのです。
「この子、ちゃんと自分でやろうとしてるんだ」と気づいたとき、私はそれまでどこかで“助けなきゃ”と先回りしすぎていた自分に気づかされました。
また、プールの帰り道に「きょう、できた」「せんせいに、ほめられた」と嬉しそうに話してくれる姿を見て、感情や経験を“言葉にする力”が少しずつ育っているのを実感。
スイミングは、身体的な成長だけでなく、理解力や表現力、そして“自信”を育ててくれる時間になりました。
こうした日々の経験や活動が、娘の理解力と語彙力の土台になっていきました。
五感を使った体験 + 誰かと関わる環境 + 安心して挑戦できる習い事。
この組み合わせが、結果的に「考える力」や「言葉を表現する力」を引き出す大きな鍵になったと実感しています。
家庭で取り組んだこと②|毎日のドリル・ワークで“思考の土台”をつくる
言葉が出てきても、「考える」「理解する」「整理する」といった力はすぐには育ちません。
再検査でIQが下がったとき、私は痛感しました。話す力”だけでなく、思考する力”も育てる必要があると。
そこで始めたのが、毎日のドリル・ワークによる家庭学習です。
そしてもう一つの鍵となったのが、「文字(ひらがな)を読む力」でした。
娘に合った教材の組み合わせ
教材選びでは、娘の好み・特性・発達段階をよく観察しながら、いくつか使い分けていました。
▷ チャレンジタッチ(進研ゼミ)
動画が大好きな娘にぴったりで、タブレットのアニメーションや音声解説にすぐ夢中になりました。



視覚優位の子にはとくに相性がよく、「見る→理解する→反応する」流れが自然に身についていったと思います。
遊び感覚で学べるので、取り組みのハードルが低く、やる気も維持しやすかったです。
また、チャレンジのいいところは、学年にとらわれず好きな学年を選択できるところ。
たとえば、年長さんでも「年中コース」を選べたり…。
- 少し戻って、確実に学習させたい
- 今の学年の内容は、まだ難しそう
そんな子でも、親が子どもの発達状況に合わせてコースを選べるので、無理せず、自信を育てながら進められます。



視覚優位のお子さんには、チャレンジタッチは、特におすすめしたい教材です。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
▷ 学研の幼児ワーク
「かわいいイラストが多く、初めてのワークとしてちょうどいい」そんな印象で、最初に取り入れやすいのが学研のワークでした。
親しみやすいイラストや色使いなので、ちえのワークを特によく使っていました。
公文の市販ドリルよりも見た目が柔らかく、ワークって楽しい!”というイメージづくりにぴったりでした。
▷ 公文のドリル(市販)
娘は公文の教室に通っていたこともあり、“公文式”のやり方に慣れていたため、市販の公文ドリルとも相性が良かったです。
反復やシンプルな構成で、取り組む手順が分かりやすいのが特徴。
とくに「読む力」「数を順に理解する力」など、基本スキルの土台づくりに向いていました。
- ドリルの対象年齢は気にしない。
- 「今の娘のできること」より、少しだけ難しい内容を選ぶ。
- がんばればできそう!と娘が感じられるレベルの問題を選ぶように心がける。



「年齢に合っていないと恥ずかしい」なんて気にしなくて大丈夫。
お子さんの“今”に合わせて選ぶことが、一番の近道です。
「できた!」「わかった!」という小さな成功体験を積み重ねていくことで、娘の自己肯定感や学ぶ意欲がどんどん育っていったように思います。
ドリル×ひらがなで理解力が育った
学習と並行して、家庭では**お風呂やリビング、ダイニングに「ひらがな表」を貼り、自然と文字に触れられる環境をつくっていました。
なかでも、絵がついたタイプのひらがな表が大活躍。
「あ→ あひる」「さ → さくら」など、ひらがなと一緒に単語とイメージを結びつけて覚えられるため、読みの力だけでなく、語彙力も同時に育っていくのを感じました。
娘は、「これは、くつ」「うさぎ、好き!」と、絵を指さしながら言葉を口にするようになり、言葉のインプットとアウトプットのサイクルが、自然とまわり始めたように思います。
娘にとって「ひらがなが読めるようになったこと」は、言葉だけでなく、理解力の伸びを加速させた大きなターニングポイントでした。
我が家が使っていたひらがな表は、ひらがなに興味を持ち始めた頃、お風呂には「うんこひらがなポスター」を貼っていました。
キャラクターのおかげで、最初の“とっかかり”としては効果抜群! 娘はお風呂のたびに笑いながら見てくれていました。



ただ、表の中身は“うんこ”がメインなので、親目線でみると読みやすさや語彙の幅という面では少し不便さも感じていました。
そこで、リビングやダイニングには、ネットで見つけた無料のシンプルなひらがな表を使っていました。
わかりやすいイラストがついているタイプを選ぶことが大事だと思いました。
このように、
- ドリルやワークで「考える力」
- ひらがな表で「読む力・語彙力」
- 絵を介した理解で「視覚からのインプット」
が連動することで、娘の理解力の底上げが進んでいきました。
家庭で取り組んだこと③|パズル・積木・図形遊びで“見て考える力”を伸ばした
わが家の家庭学習は基本的にワーク中心でしたが、気分転換や非言語的な知能(視覚や構成力)を刺激するために、パズルや図形遊びも積極的に取り入れていました。
娘はもともと療育で型はめパズルが得意だったので、興味を持ちやすく、遊びの中で“考える力”が自然と育っていったと感じます。
2歳代の療育では、アンパンマンのものを使っていました。
● 最初は「合わない教材」も。難易度の調整で興味アップ
最初に買ったのは【公文のさんかくタングラム】。
良質な教材ですが、当時の娘には少し難しかったようで、思ったよりも手が止まってしまいました。
そこで、【学研の木製かたちあわせパズルワンワンとうーたん】を購入してみたところ、ちょうどよい難易度で大ヒット!
娘が大好きなワンワンなので、「やってみたい!」という気持ちを引き出すことができました。
すごくいい商品なのに、廃盤なのか、Amazonや楽天市場になかったので、我が家は、メルカリで購入しました。
● キャラクターパズルで段階的にレベルアップ
本人のモチベーションを上げるために、好きなキャラクターのジグソーパズルもいくつか用意。
最初はピース数の少ないものから始めて、徐々にピース数を増やしながら段階的にステップアップしていきました。
最初は「ワンワン」、その次は「アンパンマン」「すみっコぐらし」や「アナ雪」など、
キャラクターの好みも、成長とともにどんどん変化していくのがとても面白く、親としても成長を感じられる部分でした。
● マグフォーマーは上級者向きだけど、図形に強い子にはおすすめ
また、知育玩具の定番【マグフォーマー】にもチャレンジしてみました。
磁石で形を組み立てる楽しさがある一方、空間認識や図形の理解力が求められるので、やや難易度は高め。
磁石でピタッとくっつく不思議なおもちゃで、平面から立体へ、どんどん形が変わっています。
図形が得意な子や慣れてきた頃に取り入れるには、とても良い教材だと感じました。
特におすすめなのが、車輪付きのセットです。
値段は正直ちょっとお高めですが、その分遊びの幅がぐっと広がります。
始めは、冷蔵庫にペタッと貼って、〇△▢などの形遊びに使うのもおすすめです。
形の認識にもつながります。
]
おわりに|子どもは変わる。家庭でも“できること”はたくさんある
「軽度知的障害」と診断されたあの日、私は不安でいっぱいでした。
でも、家庭でできることを少しずつ積み重ねた2年間で、娘は確実に変わっていきました。
教材やワークを揃えるには、それなりにお金もかかります。
でも、「今が娘のかけどき」だと信じて、迷わずかけました。
今も続けている部分はありますが、それは親にしかできないサポートだと思っています。
知能や理解力を伸ばすことも大切ですが、一番は「あなたのことを信じてるよ」と、毎日の関わりの中で伝え続けること。
その気持ちこそが、娘の心を少しずつ強くしてくれたのかもしれません。
わが家の経験が、誰かの希望やヒントになると嬉しいです。