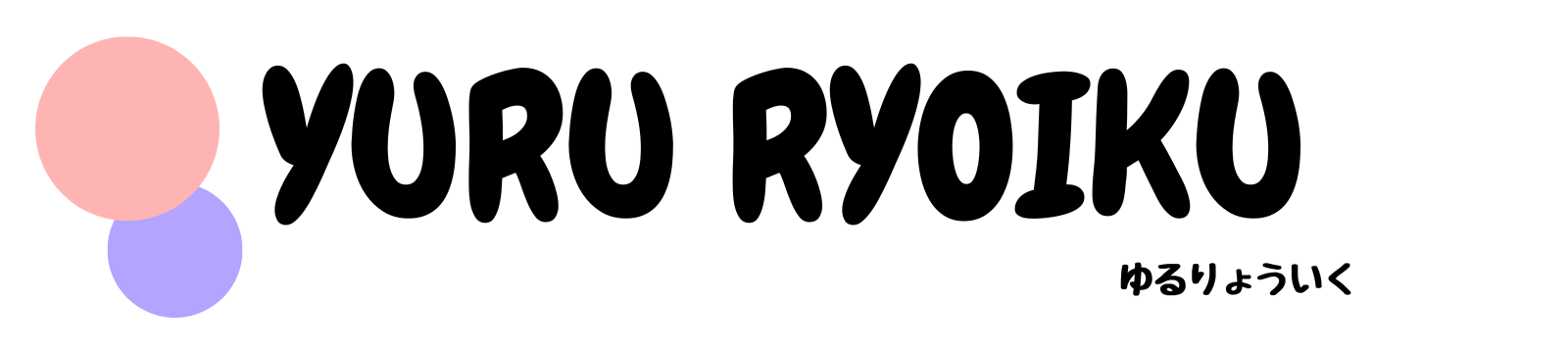こんにちは、ゆるママです。
「勉強についていけるのか心配…」
発達グレーの長男が小学校へ進学するとき、私たち家族が一番不安だったのが勉強面のことでした。
支援級ではなく、通常級でやっていくと決めたからこそ、家庭でのサポートが重要。
今回は、長男が年長から現在の小学2年生まで、どんな学習を続けてきたのか。
実際に使って効果を感じた教材や、家庭での勉強の工夫をまとめます。
家庭で予習復習を継続してきた理由
勉強の遅れを防ぐために毎日継続
我が家では、年長の頃から、体調が悪くない限りは毎日家庭学習をしています。
もちろん1日数分の日もありますが、「継続は力なり」で、とにかく毎日少しでもやることを大切にしてきました。
年長から始めた先取り学習
年長のときに、1年生の準拠ワークを買って、先取りで家庭学習をスタート。
特に算数は、つまずきそうな単元があると感じたので、早めに取り組み始めてよかったです。
教科ごとの得意・不得意と家庭学習
国語は比較的得意。漢字は得意
長男は国語が得意なタイプ。
あまり力を入れずに取り組んでも、テストで満点を取ってくることもありました。
2年生の夏休み前の漢字復習テストでも、クラスで3人だけの満点のうちの1人に入っていたようで、びっくりしました。
算数が苦手だった長男の取り組み
苦手な算数「いくつといくつ」に1年かかった話
苦手なのは算数。
特に、「いくつといくつ(5を作るには2と3、など)」の単元は、年長から取り組んでもまったく理解できませんでした。
一度期間を空けてから再挑戦したり、繰り返し説明したり。
結局理解できたのは、小学校で習う直前のタイミングでした。
早くから教え始めてよかったと心から思いました。
 ゆるママ
ゆるママ1年かけてやっと理解したこの単元。今でも苦手意識があるようで、久しぶりに出題すると、まだ間違えることもあります。
計算は「努力でカバーできる」から武器に
長男は算数の文章問題の読み取りには苦手さがありますが、計算については努力で伸ばせる部分だと感じています。
だからこそ「計算は強みにしていこう」と、公文教室に通わせています。
繰り返しの学習に強い公文は、長男に合っていたようで、少しずつ計算への自信がついてきました。
「計算は、努力でカバーできる」



算数全体が苦手だと勉強が嫌いになってしまうと思ったので、「ぼくは、計算が得意」と自信を付けてもらいたいです。
1年生の長期休みは、復習と予習に使った
- 夏休み:7月は復習、8月は予習と復習半々
- 冬休み:12月は1・2学期の復習、1月は3学期の予習
- 春休み:1年の総復習+2年生の予習(漢字・算数)
定期的に振り返り、次に備える学習を意識していました。
使ってきた教材と選び方の工夫
チャレンジタッチは年長で活用、その後紙教材へ
長男は視覚優位タイプなので、タブレット学習のチャレンジタッチは年長の時期にとても効果的でした。
でも、小学生になると紙の教材のほうが合っていると感じました。
苦手な単元は、とことん繰り返す必要があるため、親が調整できる市販のワークが向いていると思いました。
チャレンジタッチは、視覚優位の子におすすめ!子どもが楽しめる内容で、勉強の習慣をつけやすいです。
準拠ワークや市販ドリル、公文で力をつける
我が家では、以下の教材を使い分けています。
- 教科書準拠ワーク(学校と同じ進度)
- 市販のドリル(苦手をなくす)
- 公文教室(計算に特化)
教科書準拠ワーク
準拠ワークは、学校の教科書に合わせて作られているので、授業の流れに沿って取り組めるワークです。
勉強が苦手な子で、市販のワークで何をかえばいいの?と悩んでいる方には、まずこのタイプがおすすめです。
長男が実際に使っているのは、こちらです。
※お子さんが通っている小学校によって、教科書の出版社が違います。間違えないように、注意してください。
おすすめ算数市販のドリル
120までの大きい数に特化したワーク。
数表、大きい数を数える、大きい数のあらわし方、大きい数の計算など、大きい数だけでいろんなパターンの問題があります。
大きい数はつまずきやすいポイントだと思います。長男も、このワークをコピーして何度も解きました。
文章題にぐーんと強くなる
1年生のときは、文章題も教科書準拠ワークのもの解かせていました。



算数の苦手が多すぎて、文章題だけの問題集に取り組む余裕がありませんでした。1年生は、教科書と準拠ワークを完璧にを目標にしていました。
ただ、準拠ワークだけだと問題数が少ないので、物足りないと感じました。
できるなら、文章題に特化したドリルにも取り組みたいと思い、2年生になって新しく取り入れました。
このドリルは、似たような問題がたくさんあるので、問題に慣れる練習になると思います。
単位と図形
先ほどの文章題と同じシリーズの単位と図形のドリルです。
こちらも2年生で取り入れました。
2年生で、単位と図形だけでそんなに問題あるのかな?と思っていたのですが、中を見ると、すごくいい!
時間、長さ(mm、cm、m)、かさ(LとdL)、図形など。



後半の図形の問題は、長男の苦手を詰め込んだような問題ばかり…。
これは苦戦するだろうなぁ。と思いながらも、少しずつ進めていこうと思います。
算数のつまずき対策に親が読んだ本
長男はWISCなどの検査は受けたことがありませんが、ワーキングメモリが低いのでは?と感じることがあります。
だからこそ、つまずきの理由を知る本を読んでみました。
ワーキングメモリ視点で“つまずき”を知る『ワーキングメモリを生かす 数・計算の教材』
数や計算のつまずきをワーキングメモリの視点から解説。教え方の見直しにおすすめです。
『ワーキングメモリを生かす 文章題・図形の教材』
図形・文章題が苦手な子にも役立つ。なぜ苦手なのか?が見えてくる支援のヒント本。
2冊とも同じシリーズで、つまずいている“理由”を理解して教えるという新しい視点をくれる本です。
正直、まだ長男の2年生前半では、はっきり効果を感じるわけではないけれど、「ここでつまずきそう」と予想して備えています。
発達ゆっくりの子は、教え方によって、理解、伸びが変わります。



つまづいたときに、サポートの方法を知っていると対処もしやすいので、このシリーズの本は読んでおいて損はない1冊だと思います。
努力で前に進む長男の姿勢
問題の量をこなすことで理解を深める
長男は、一度で理解できるタイプではありません。
でも、不器用なりに、とにかくコツコツ頑張るタイプです。
似たような問題でも、出され方が少し違うと戸惑ってしまうことも多いので、数をこなして慣れるようにしています。
この努力量は、ほんとうに親として誇りに思うところです。
2年生の春、先生から言われた言葉
2年生になって初めての面談で、先生から
「算数のプリントがクラスで5番目くらいに早く終わってますよ!」と教えてもらいました。



算数に苦手意識があっただけに、とても驚きましたし、家庭で予習してきた成果が出ているんだと実感しました。
おわりに
発達グレーと言われる長男が、通常級で学び続けるために、家庭でできることを、できる範囲で続けてきました。
うちの子は、特別な才能があるわけではありません。
ただ、「できないことは人より多いかもしれないけれど、それでも努力で補えることもある」ということを、日々実感しています。
算数にしても、国語にしても、得意・不得意はあって当然。
でも、そのつまずきを放っておかず、「親が気づいて、どう支えるか」を考えてきたからこそ、少しずつ力がついてきたのだと思います。
今できていなくても、いつかできるようになる。
そう信じて、これからも長男に合ったペースで、伴走していきたいと思っています