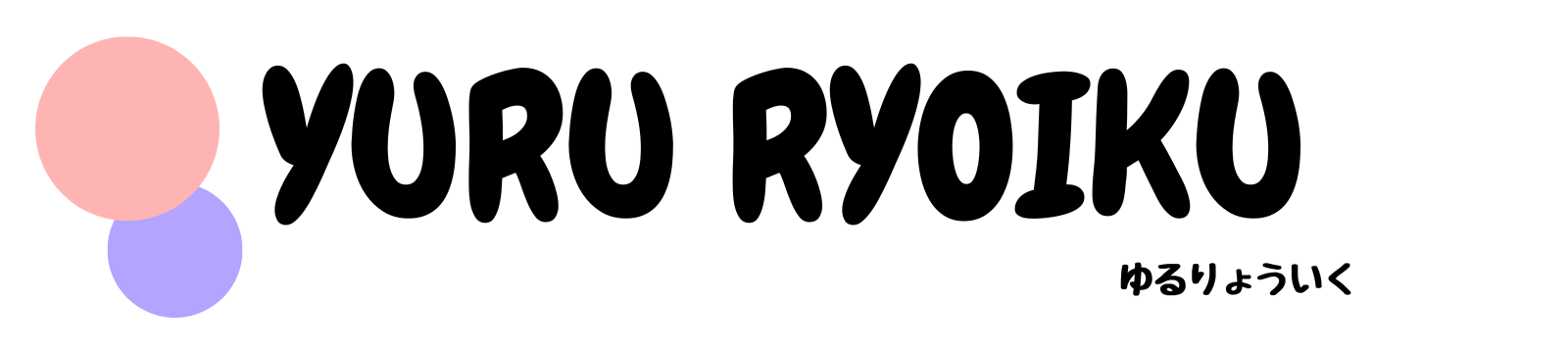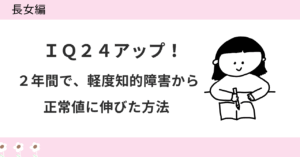こんにちは、ゆるママです。
我が家には3人の子どもがいます。
上2人は、いわゆる“発達グレー”と言われるタイプ。
長女にいたっては、当時「軽度知的障害」の診断も受けていました(のちに正常値に)。
そんな背景があるからこそ、3人目の育児では発達面でかなり意識的に関わってきました。
今回は
 ゆるママ
ゆるママ「上の子がグレーだからこそ、3人目の発達をどうサポートしてきたか」を記録としてまとめておこうと思います。
1歳半までは常に“気にする育児”
1歳半で単語が出ても安心できない
末っ子が生まれてから、私は常に「発達を見逃さない」目で育児をしてきました。
というのも、長男・長女のどちらも、1歳半健診の時点では、一応3単語は出ていたからです。



つまり、「1歳半で単語が出ている=安心」ではないと経験から知っていたから。
末っ子の発語が早くても常に観察
末っ子も、10ヶ月ごろから発語が出ていたから、発達が早いのかもと期待はしていたけれど、それでも油断は禁物!と安心はせずに、ずっと発達の様子に気を配ってきました。
こちらの記事で、長女の5歳までの発達について書いています。


テレビ・タブレットはほぼゼロで育てた
テレビなし育児で育った末っ子
我が家にはテレビがありません。
長男が4歳、長女が2歳のときにテレビを処分したため、末っ子は生まれてから一度もテレビのある生活を経験していません。
タブレットも最小限に
タブレットも、1歳ごろまでは一度も見せず、1歳を過ぎてからも週に2〜3回、30分程度見せるかどうか。
絵本好きな子に育った
その代わり、絵本をたくさん読み聞かせるようにしました。
結果、絵本が大好きな子に育っています。
「動画を見せない育児は正解だったか?」という問いにはまだ答えは出ませんが、



絵本好きで言葉がどんどん出てきた姿を見ると、我が家にとってはいい影響だったのではと感じています。
1歳8ヶ月の今は、なかわみわさんの絵本がお気に入り



話の内容は理解していないと思いますが、絵がかわいいのと日常でよく見るものが出てくるので、興味津々で見ています。
Alexa(アレクサ)を活用!童謡シャワーの毎日
毎日童謡を流して親子で歌う時間
上の子たちと違うのは、我が家にAlexa(アレクサ)があること。
末っ子が生まれてから、AmazonのAlexaで、毎日童謡を流して一緒に歌う時間を作っています。
1歳半で5曲のワンフレーズが歌えるように
童謡やプリキュアの曲などをかけて、親子で歌って踊る毎日。
その影響もあってか、1歳半ごろにはワンフレーズで5曲ほど歌えるようになりました。



上の子たちが小さいときにアレクサがあったら、もっと遊びに音楽を取り入れられたかも…と思うほど。
一時保育で“家庭外の刺激”を意識的に
長女の経験から家庭外の重要性を学んだ
長女は、言葉が出ないことを気にして、2歳半ごろから慌てて、一時保育を利用するようになりました。
そのときに、「家庭外の刺激って、発達を促すのに大事」と感じました。
1歳3ヶ月から定期的に一時保育スタート
そこで、末っ子は上手に歩き始めた1歳3ヶ月ごろから、定期的に一時保育を利用することに。
我が家は両家の実家が遠方で、祖父母との接点も少ないので、家族以外の人との関わりは貴重。



ママと2人きりでは、どうしても語彙や会話の幅も限られてしまうため、外の人を頼る選択をしました。
「育て直し」のような感覚もあった
療育経験から得た知識と実践
上の子2人のときにはなかった知識や視点が、3人目の育児にはあります。
「この遊びは発達にいいらしい」「こういう声かけが効果的らしい」など、療育で得た情報をもとに、意識的に遊びや関わりを変えてきました。
加えて、上の子たちの療育で実際に使っていたおもちゃも、赤ちゃんの頃から用意しました。
くるくるチャイムは、今までに4ヶ所通ったすべての療育施設にありました。
始めは、ただボールを入れて、くるくる出てくるボールをみるだけのおもちゃと思っていました。
しかし、シンプルな動作ですが、ボールをにぎり、ねらった位置で手をはなし、ボールが転がる様子を目で追うという乳幼児の「できること」を考えて設計されています。



購入してから1年が経つ今でも、夢中になって繰り返しボールを入れている姿を目にします。
アンパンマンの型はめパズルは、2歳の長女が初めて通った療育(児童発達支援)で、お気に入りでした。
発達情報を避けず、積極的に調べた
反応の引き出し方や遊びの広げ方も経験値として活かせたのは、3人目ならではだと思います。
また、



以前は「調べすぎると気にしすぎるから」と、あえて発達の情報を遠ざけていた私ですが、今回は違いました。
発達の進み方についての本も読み、早いうちからサポートできることがないか意識的に探していました。
上の子たちは2歳と4歳から療育に通い始めたので、そのくらいの年齢のかかわり方は、なんとなくわかっていました。
しかし、



0歳~の育児となると、上の子たちの発達のこともあり自信がありませんでした。
「0~4歳ことばをひきだす親子遊び」の本は、私が一番心配していた言葉に焦点を当て、具体的な遊び方を教えてくれました。
規則正しさにこだわりすぎない暮らしへ
過去の反省から柔軟な生活リズムへ
上の子たちの育児では、生活リズムを整えることを強く意識していました。



特に昼寝の時間を守るために、外出時間を短時間に抑えたり、それが言葉の発達にとってはマイナスだったかも…と、今になって反省しています。
今回は、規則正しい生活を意識しつつも、「昼寝を最優先にしすぎない」柔軟さを持つようにしました。
外出・イベント参加で刺激ある日常に
未就園児向けのイベントや地域の集まりにも積極的に参加し、家の外でもたくさんの人と触れ合う機会を作るようにしています。



そもそも3人目ともなると、平日はほぼ毎日、上の子たちの幼稚園の送り迎えや習い事の送迎があるため、家にじっとしているほうが難しいんですよね。
兄姉のおかげで自然に言葉が増える環境に
そのぶん、お兄ちゃんやお姉ちゃんの周りにいる大人や子どもたちから声をかけてもらったり、一緒に遊んでもらったりと、自然と刺激のある日常に。



実際、末っ子の言葉の発達はとても早く、こうした生活スタイルも大きく影響しているのかもしれません。(たまたま発達が早いだけかもしれませんが…)
「できることをする育児」で十分
我が家の3人目育児は、上の子たちの経験を糧にした“育て直し”のような部分もありました。
だからといって、完璧ではありません。
どんなに知識があっても、子どもはその通りには育ちません。
でも、できる範囲でできることをやる育児で、十分だと思っています。
発達が気になる子を育てたからこそ、次の子で工夫できることがあった。
それは、決して悪いことではなく、大切なことだと今は思います。