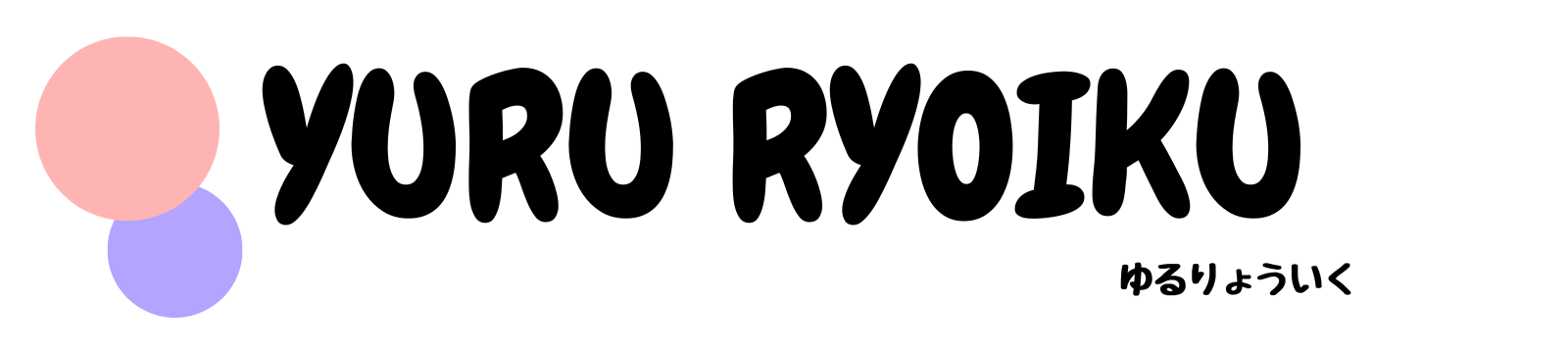現在小学2年生の長男は、いわゆる発達グレーのタイプ。就学前の相談はせず、通常級を選びました。
通常級を選ぶと決めたとき、「勉強面はしっかりサポートしよう」と親として覚悟していました。
 ゆるママ
ゆるママでも、いざ学校生活が始まってみると、勉強以外でも困ることが思いのほか多くて…。
今回は、そんな「勉強以外の学校生活のリアル」についてまとめてみます。
忘れ物、整理整頓、体育の壁や友達関係…日々の小さな困りごとと、我が家なりの工夫を記録しておきます。
同じように「通常級にしようかな」と悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
地味に一番大変?忘れ物との戦い
入学後から悩んでいることは、「宿題を学校に忘れて帰る」こと。
親がチェックできるのは、家から学校へ持って行く荷物まで。
学校からの持ち帰りは本人の管理なので、これがなかなか難しい。
特に宿題のプリントは、机の中が散らかっていると気づきにくいようで、しょっちゅう置きっぱなしに。
結局、親子でわざわざ学校に取りに行く羽目になりますが、下の子2人を連れて行くのは本当に大変。
特に雨の日は最悪で、「傘、抱っこ、荷物…手が足りない!」と心の中で叫んでます。



もう少し確認してから帰ってきてよ…
とつい小言を言ってしまう日々です。
上履きや給食袋の管理



上履きは「2週に1回持ち帰ってくればOK」と、ある程度割り切るようにしました。
給食袋は毎日使うので、3セット用意して、1日忘れても大丈夫な体制に。
傘や水筒は意外と忘れない
よく聞く「傘忘れ」は、今のところゼロ。
水筒もまだ1度も忘れていません。
ここは長男の得意な部分なのかもしれないな、と少し嬉しく感じています。
文房具やノートの備えも大事
「ノートがない」「のりがない」と、ある日突然言われることがよくあります。
何度近くのスーパーに買いに走ったことか…。
慌てないためにも、ノートやのりは予備を用意しておくのがおすすめ。



急に言われてもストックがあれば安心だし、親の心の平穏のためにも「多めに用意」は必須だなと感じています。
机の中や筆箱の中がカオス
参観日・面談で判明した机の中のカオス
参観日や面談で机の中をのぞいたら…ものすごく散らかっていてびっくり。
「どこに何があるのかわからない」状態で、本人はあまり気にしていない様子。
これは本人の整理整頓スキルの課題として、少しずつ意識を持たせていきたいところ。
家で筆箱の中身をチェック
帰宅後に筆箱を開けてみると、えんぴつも消しゴムも入っていないことがよくあります。
忘れてきたのか、どこかでなくしたのか……もはや本人も分かっていない様子。



毎日のように何かが減っていくので、親としては地味に出費が痛い。
「また消しゴム買わなきゃか〜」と、心の中でため息をつく日々です。
えんぴつ、消しゴム、のり等の文房具は、ストックしています!
連絡袋やプリント類の管理もひと苦労
うちの小学校では、学校指定のファスナー付き連絡袋があるのですが、あのファスナーの開け閉めが長男にはちょっと手間だったようで、テストやプリントを入れずにそのままランドセルへ直INされてしまうことが多くて…。
ぐちゃぐちゃになったテストやお知らせプリントが出てくるたび、「もう少しちゃんと入れてくれたら…」と思ってしまいます。
そこで、ファスナーなしで挟むだけのシンプルなファイルに変えてみたところ、最初の1ヶ月くらいはしっかりそこに入れて持ち帰ってきてくれました。
でもそのうち「入れるのが面倒くさい」になったようで、やっぱりランドセル直INに逆戻り…。
結局、道具の工夫だけでは解決しない、「めんどくさがりや気質」という根本があるのかもしれません。
お道具箱の中も事件だらけ
お道具箱の中身も、なかなかにカオスです。



クレヨンやクーピーがバラバラに散らばっていたので、クレヨンにはゴムでまとめる工夫をしてみたのですが、夏休みに持ち帰ったお道具箱を見てみたら、ゴムが消えていました。笑
クーピーに至っては、4本しか入っていない…!
どうやら先生が一緒に片づけてくれたようで、翌日には残りを持ち帰ってきました。



こういうトラブルが続いたので、2年生からはクーピーをやめて、色鉛筆に変更しました。
色鉛筆は折れにくいし、なんと長男、自分で家に持ち帰って削って、また学校に持っていくという行動ができるように。
「え、これは自分でできるんだ!」と、ちょっとした成長にびっくりした出来事でした。
▼長男が使っているものは、こちら。
色鉛筆が、1本ずつしっかり固定されるケースなので、バラバラ落ちる心配がありません。
ケースは、プラスティック製で、金属缶のように落としたときに大きな音がしないのもポイント



よく物を落とす長男には、ぴったりの色鉛筆でした。
体育の壁と家庭でのサポート
1年生の体育でできなかった長縄
1年生のとき、体育の授業で「長縄に入って飛び、出る」動作ができなかった長男。



実はクラスで一人だけできなかったらしく、1年生最後の面談で先生から知らされました。
「もっと早く教えてくれたら…」という思いは正直ありました。
家族で練習して、2年生でできるように
ネットで長縄を購入して、家族で特訓。
すると2年生の体育で成功し、先生にも褒めてもらえました。
家族の努力が実を結んだ瞬間でした。
運動面のサポート、どこまで必要?



勉強面はある程度親も覚悟していたけれど、運動面はどこまでサポートが必要か判断が難しい。
鉄棒、縄跳び、マット運動…これから先も課題は続きます。
「一人だけできないのはかわいそうかな」と思い、鉄棒やマットは家で購入して、たまに練習。
でも、本人はあまり好きではなくて…。
とはいえ、周りの子ができるようになれば、きっと焦って練習しはじめるだろうなぁと、気長に見守っています。
▼わが家で使っているマットと鉄棒はこちら
友達関係のモヤモヤと嬉しさ
遊ぶ約束の曖昧さ
2年生になってから、「お友達と遊ぶ約束してきた!」と嬉しそうに帰ってきます。
でも、「土曜日?日曜日?」「何時?」が全然わからず、予定が立たないのが悩みどころ。
親のフォローは必須です。
それでも、友達がいる嬉しさ
でも、仲の良い友達ができたのはとても嬉しい。



「遊ぶ約束をしてきた」というだけでも、親としては感動なんです。
「できない」だけじゃない、日々の成長
通常級で過ごすなかで、苦手なことは確かにあります。
でも、それだけではない。ひとつずつ、家でも学校でも、できるようになることが増えていっている。
勉強も生活も、時間がかかっても「前に進めている」と感じられるようになりました。
この先も親子で向き合いながら、一歩ずつ進んでいけたらと思っています。