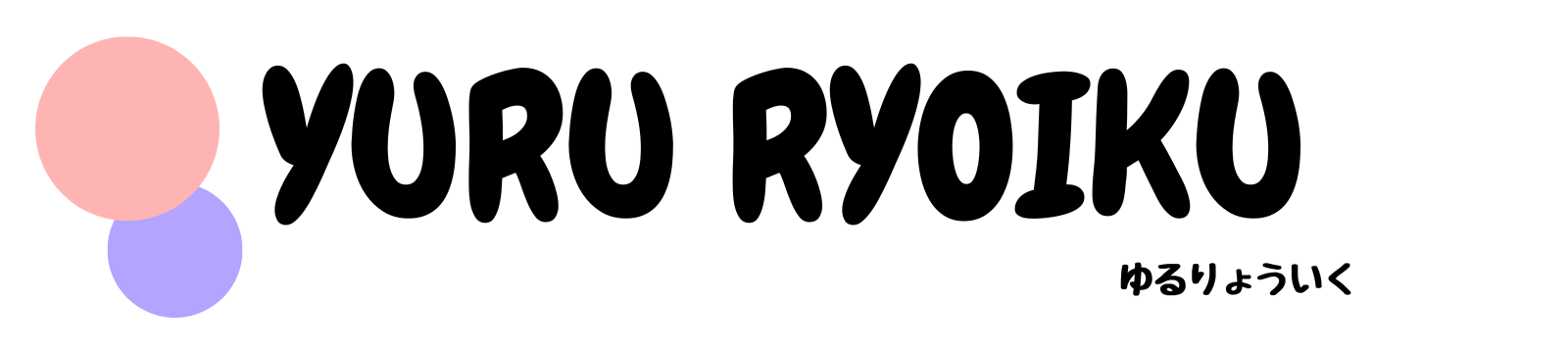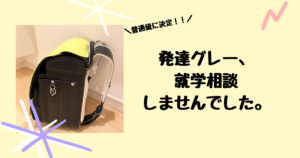こんにちは、ゆるママです。
発達グレーゾーン・境界知能の子どもが小学校に進学すると、親が一番気になるのが 「宿題をきちんとこなせるのか?」 ではないでしょうか。
 ゆるママ
ゆるママ我が家の長男も境界知能で、就学前は「宿題に苦労するかもしれない」と心配していました。
ところが、



実際には、「帰宅後すぐに宿題をするルーティン」 を徹底したことで、想像以上にスムーズに進められています。
今回は、長男の宿題内容(小1〜小2)と、わが家で実践しているサポート方法をご紹介します。
目次
小学1〜2年生の宿題の内容
小1の宿題
- 音読:毎日
- 計算カード:足し算・引き算が始まったタイミングからスタート
- プリント:国語か算数のプリント1枚
1年生の初めは音読だけでしたが、途中からプリントが追加。
後半には 音読+プリント+計算カード が定番になりました。
内容は比較的やさしく、大きな苦労はありませんでした。
小2(1学期)の宿題
- 音読:毎日
- プリント:国語か算数のプリント1枚
この時期は宿題の量が少なめで、ほとんど自力で進められる内容でした。
小2(2学期以降)の宿題
- 音読:毎日継続
- プリント:国語か算数のプリント1枚
- 計算カード(九九):掛け算が始まったタイミングで追加



九九カードが始まると少しハードルが上がりそうですが、習慣化しているため対応できそうです。
わが家の宿題サポート法
1. ルーティン化がカギ
長男は「ルールを守る」ことが得意なタイプ。
その特性を生かして、入学直後から「帰宅したらまず宿題」 という流れを徹底しました。



その結果、学校から帰ってくると自然に机に向かい、親が声をかけなくても宿題を始めるようになりました。
2. 実際のサポート手順
- 音読 → 聞いてあげて、日付とサインのみ
- プリント → まず自分で解かせ、難しければ隣でサポート。最後に答え合わせ
- 計算カード → 初めは親がカードをめくり、テンポよく答えられるようサポート
基本的には 「ほぼ自力」+「困ったときだけ手助け」 というスタンスで取り組んでいます。
宿題で困らなかった理由を振り返って
- 宿題の量が多すぎなかった(学校によって差があるので、うちはラッキーでした)
- 「宿題→明日の準備→おやつ」 というルーティンが定着した
- 親は「全部一緒にやる」のではなく「困ったときだけサポート」に徹した
この3つが揃ったことで、宿題はスムーズに習慣化できました。
まとめ
- 発達グレーの小学生でも、宿題はルーティン化すれば自分で進められる
- 学年ごとに宿題の内容が変わるので、親は先を見通して準備しておくと安心
- 「毎日がっつり一緒に」より「困ったときだけサポート」 が自立を促すコツ
宿題は学習の基盤でありながら、家庭でのストレスになりやすい部分です。
だからこそ「量」「ルーティン」「サポートの線引き」を意識することで、発達グレーの子どもでも負担を減らして取り組めると実感しています。
あわせて読みたい




発達グレー小2、通常級で勉強についていけている家庭でのサポート
発達グレーの長男が学ぶために、家庭ではどんなサポートをしてきたか。苦手な算数のつまずき、予習復習の工夫、使ってよかった教材などを記録していきます。