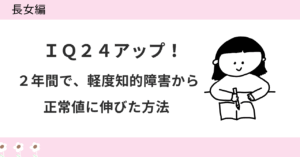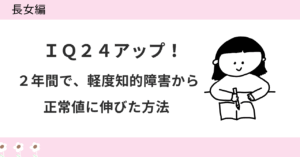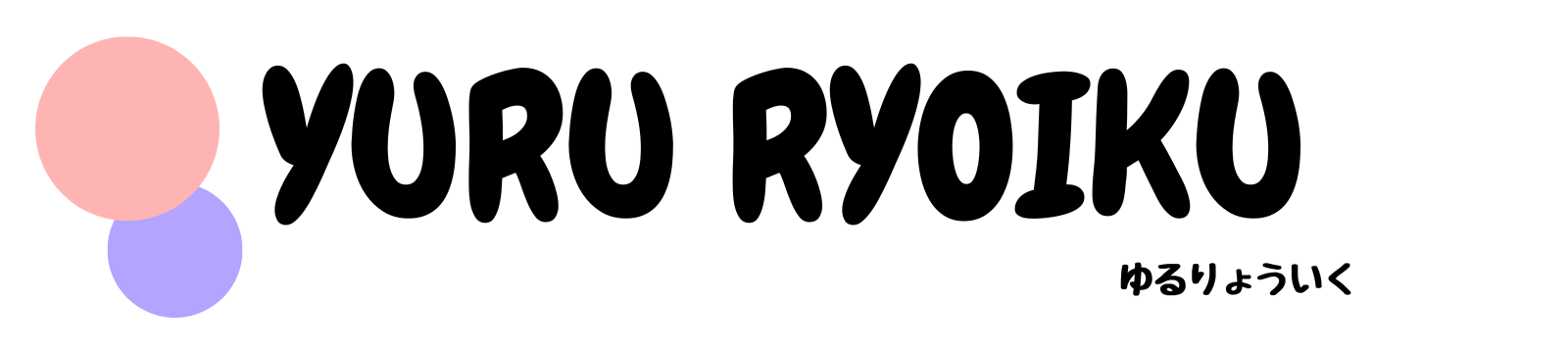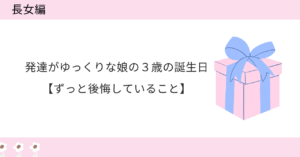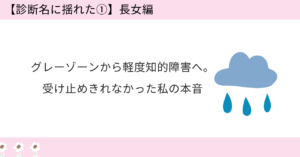こんにちは、ゆるママです。
子どもが発達検査を受けると、必ず出てくるのが「IQ(知能指数)」や「DQ(発達指数)」といった数字。
数値が思ったより低いとショックを受けたり、逆に高いと安心したり…
親としてどうしても一喜一憂してしまいますよね。
私自身も、長女の発達検査で数値が下がったときには大きなショックを受けました。
逆に伸びたときには「よかった!」と安心し、気持ちが揺れ動いた経験があります。
けれど、今振り返ると「数字だけに振り回されなくても大丈夫」だと思えるようになりました。
この記事では、私の体験を交えながら
- 発達検査のIQやDQは本当に伸びるのか?
- 検査結果に一喜一憂しないための親の視点
についてお伝えします。
発達検査の「IQ」に振り回された私の経験
子どもが検査を受けると、必ず数値が出ます。
 ゆるママ
ゆるママ「IQが低いからできないのかな?」と考えすぎてしまったり、逆に「少し上がったから大丈夫かも」と安心したり…。
私も長女が小さい頃は、完全に数値に心を揺さぶられていました。
でも実際には、IQやDQは伸びることもあれば下がることもあります。
大切なのは、数字そのものではなく「数字の奥にいる子ども自身をどう見つめるか」だと気づきました。
IQは本当に伸びるの?体験から学んだこと
数値が下がってショックを受けたとき
長女が2歳で受けた初めての検査はDQ76。
しかし1年後、3歳のときにはDQ68まで下がり、「軽度知的障害」と診断を受けました。
「わずか1年でこんなに下がるの?」と当時は大きなショックを受けました。
その後、大きく伸びた経験
けれど、療育や家庭での関わりを続けるうちに、5歳で受けた検査ではIQが24も伸び、正常値になりました。
この経験から、



検査結果は「変わるもの」であり、未来を決めつけるものではないと実感しました。
検査結果は“今の子どもの写真”にすぎない
発達検査の数値は、その時点での子どもの一部を切り取った“写真”のようなものです。
もちろん、結果に落ち込んだり喜んだりするのは自然なこと。
でも、その1枚の写真だけで子どもの未来を決めてしまう必要はありません。
IQより大切なこと|子どもが生きやすくなる力を育てる
IQを伸ばすことを目的にしない
私自身、かつては



「IQを上げたい!」という気持ちで関わっていた時期がありました。
でも、今振り返ると大切なのは数値ではなく「この子が生きやすくなる力を育てること」だと感じます。
生きやすさを育てるサポート例
- 言葉の理解や表現を少しずつ増やす
- 数や生活動作を練習し、困らない場面を減らす
- 得意なことを見つけ、自信につなげる
- 経験や体験を積み重ね、感情や語彙を広げる
これらは定型発達の子にも共通することです。



「必要な力を少しずつ積み重ねる」ことが、結局は一番の近道。
そしてその過程で、結果的にIQが伸びることもあるのです。
数字に振り回されそうになったら
一喜一憂するのは自然なこと
検査結果を見て、落ち込んだり喜んだりするのは「子どもの未来を本気で考えているからこそ」。
自分を責める必要はありません。
数字を横に置いて、日々の成長を見つめる
「昨日できなかったことが今日できた」
「初めて自分から声を出した」
「楽しそうに活動している」



そんな“数値では表せない成長”に目を向けてみると、親子の時間がずっと豊かになります。
まとめ|IQは伸びるけれど、それ以上に大切なこと
- 発達検査のIQやDQは、伸びることも下がることもある
- 結果に一喜一憂するのは自然なこと。親が子どもを大切に思っている証
- 本当に大事なのは「数字」ではなく「子どもが生きやすくなる力」
- IQの伸びは、そのサポートの積み重ねの“副産物”として現れることもある
子どもの数値に振り回されそうになったときこそ、数字を一旦横に置いて「その子自身の成長」に目を向けてみてください。
きっと未来は少しずつ変わっていきます。