2歳の発達検査で、境界域だった娘。いわゆるグレーゾーン。
少しずつ言葉も増えて、「きっと伸びてる」と信じていた3歳で受けた発達検査。
2回目の発達検査で告げられたのは「軽度知的障害」という結果でした。
今回は、あのとき私が感じた衝撃、戸惑い、そして“障害”という言葉とどう向き合ったかを正直に書きます。
「前よりできることが増えているのに、なぜ?」
そう感じたあの日の私のように、診断名に悩む誰かの心に、少しでも届いたらと思います。
発達検査に込めた小さな希望と不安
発達検査の結果を聞くときには、いつもすごく緊張します。
そして同時に、ほんのわずかでも希望を持ってしまいます。
「前より、伸びているかもしれない」
「少なくとも、下がることはないはず」
今回の検査は、長女が3歳になって受けた2回目のものでした。
長女は、2歳のとき、最初の発達検査で“境界域”とされる数値を出していました。
いわゆる「グレーゾーン」。障害とまでは言えないが、正常とは言い切れないライン。
今回は、きっと大丈夫。
少しずつ話せる言葉も増えてきたし、身の回りのこともできることが増えていました。
「きっと、今回は伸びてる」そう信じていました。
そんなわずかな希望を抱きながら臨んだ3歳の発達検査でした。
「軽度知的障害」の言葉に、思考が止まった
でも、現実は、真逆でした。
結果は、「軽度知的障害」。
前回より、数値は下がっていました。
そんなはず、ない。
思考が止まり、目の前の結果の紙を、ただ呆然と見つめるしかありませんでした。
前よりできることが増えたのに
「伸びていなかった」という現実よりも、「下がっていた」という事実が、重く感じました。
あんなに療育に通ったのに。
前より、できることは確実に増えているはずなのに。
語彙も増えたし、こちらの指示もきちんと通る。
毎日そばで見てきた私が、一番わかっていたつもりでした。
数字で評価されることの怖さ
それなのに、数字は、それを「成長」と認めてくれませんでした。
まるで、娘の歩みが否定されたように感じた。
ほんの数ポイントの差。
でも、それが「グレーゾーン」と「軽度知的障害」の境界線でした。
目に見えないたった一本の線。
それを越えただけで、世界の見え方が変わってしまった気がしました。
検査結果の紙を前に、私は感情をどう扱えばいいのかわかりませんでした。
悔しさ、悲しさ、怒り。
どれもあるけれど、どれでもない。
一番近いのは、おそらく恐怖でした。
この先、どうなるのだろう。
この子の未来は?小学校は?友だちは?
「数字がすべてじゃない」
そう思いたい。
けれど、現実にはその数字が、療育の方針を決め、支援の有無を左右し、就学先の選択にすら影響を与えます。
「軽度知的障害」
その診断名がついた瞬間、私は打ちのめされていました。
この診断名を、私は誰にも言えなかった
「軽度知的障害」
その言葉を、私は夫以外、誰にも言えずにいました。
目の前にいる娘は、今日も笑っている。
幼稚園では、お友だちと楽しそうに遊び、先生にもしっかり返事をする。
困っていることが全くないとは言えないけれど、それでも日々、確かに成長していました。
検査の数値。
発達の凸凹。
「たしかに違和感はあるけど、そこまでではないよね」と、
曖昧にされてきたグレーのラインを、こんどははっきりと超えたという事実。
それでも「軽度知的障害」という言葉は、世間にも私自身にも重すぎました。
もし誰かに話せば、きっと励ましの言葉が返ってきたでしょう。
でも、私は、その励ましが怖かったのです。
「そんなふうに見えないよ」
「きっと普通になるよ」
そう言われた瞬間、さらに苦しくなる気がしたのです。
私は、自分自身が「障害」という言葉に引っかかっていました。
数字で線引きされるこの世界が、残酷だと感じました。
あんなに頑張ってきたのに。
前よりずっとできることが増えたのに。
なのに、前よりできない子として、ラベルを貼られたような気がしました。
しかし、私がどれだけ戸惑っても、落ち込んでも、目の前のこの子が過ごしやすい環境をつくるために、
「診断名」というパスポートが、必要でした。
私はこの現実を、心の奥で少しずつ少しずつ、飲み込もうとしていました。
下がった数値より、目の前の「できた」を信じたい
落ち込んでいたはずなのに、心の奥ではずっと引っかかっている感情がありました。
あの子、前より確実に伸びている。
数値は下がった。診断名は「軽度知的障害」。
けれど私の目には、どう考えても成長しか映っていませんでした。
語彙も増えた。
理解力も上がった。
やり取りは2歳の頃とは比べものにならないほど滑らか。
それなのに検査は、「できていない部分」にだけ光を当てます。
得意よりも、苦手を強調します。
当日の体調や気分、検査者との相性でさえ左右されるはずなのに。
もちろん長女には、まだ苦手は多いです。
だが苦手=障害ではない。
私は、数字とは別に、目の前の娘を見つめようと必死でした。
「大丈夫、きっと伸びる」
そう思うことで、自分を支えていたのだと思います。
発達検査の数字なんてどうでもいい
これだけ成長した姿を数字が拾えないのなら、数字なんてどうでもいい。
そんな投げやりな怒りさえ湧いていました。
「この子の伸び」を認めようとしない検査結果に、強い反発を覚えました。
だから私は、診断名を一度脇に置きました。
代わりに、娘の「できた」を拾い集めることに決めました。
今日できたボタンかけ。
昨日より長く続いた会話。
自分から幼稚園で何をして遊んだか教えてくれたこと。
小さな「できた」は確かに積み重なっています。
たとえ数値が示さなくても、ここにある成長だけは信じようと思いました。
その確信だけは、どうしても手放したくありませんでした。
この子を障害児にしたくないという、母としての本音
“障害”という言葉への抵抗
それでもやっぱり、「障害」という言葉には、どうしても引っかかっていました。
数字では測れないこの子を見ようと思っても、胸の中のモヤモヤは消えませんでした。
検査結果を聞いてからというもの、私は自分に問い続けました。
私は、わが子が“障害児”と呼ばれることを受け入れ切れていないのでは?
実際、目の前の娘は伸びている。
語彙も増え、できることも増え、表情だってずっと豊かになった。
なのに「軽度知的障害」というラベルを貼られることに、強い違和感と反発心が湧きました。
正直、この言葉を受け入れたくありませんでした。
差別と言われるかもしれない。
けれど母親として願うことはただ一つ。
「どうか、この子を“障害児”にしないでほしい」
そう思いながら、私はある意味で割り切る道を選びました。
診断を最大限に活かすために
娘を“軽度知的障害”とするのなら、その診断で得られる支援や制度は最大限に活かそうと思いました。
療育手帳、各種割引。
この子の未来を守るカードなら、遠慮せず使うと、決めました。
強さと弱さが、私の中で同居していました。
診断を受け止め切れない自分を責める気持ち。
母親なのに障害を受け入れられない私は間違っているのでは?という自己嫌悪。
それでも私は、自分の“受け入れられない”気持ちと、「この子のために行動する」気持ちの両方を抱えながら、
少しずつ現実と折り合いをつけていきました。
「診断名は、娘のすべてじゃない」
療育手帳を取得して、私はこの子を「障害児」にしてしまったのかもしれない。
でも、それで娘の何かが変わったわけではありませんでした。
療育手帳を取得しても、娘は何も変わらない
娘は、相変わらず、朝はのんびりしていて、気分屋で、好きな歌がかかると急に踊り出します。
おしゃべりも増えてきて、ちょっとした冗談を言うようになりました。
一緒に笑ったり、怒ったり、拗ねたりして過ごす日々は、以前と何も変わりません。
変わったのは、たった一枚のカードと、「障害児」というラベルを貼られた、という現実だけでした。
療育手帳は、あくまで“制度のためのカード”でしかありません。
手帳を持ったからといって、この子の性格や未来が決まるわけじゃありません。
むしろ、支援を受けやすくなることで、この子が生きやすくなるならそれでいい。
私はずっと「障害」という言葉に引っかかっていたけれど、少しずつ、この言葉と長女の姿が、別のものだと思えるようになってきました。
きっかけは特別な何かじゃありませんでした。
ただ、いつも通り幼稚園に行って、療育に通って、習い事をして、いつもの日々を過ごすうちに、心の中のわだかまりが少しずつ溶けていきました。
あの日、検査の結果を聞いたときの衝撃は、今も忘れていません。
でも、時が経ち、日常が続いていくなかで、私は自然と気持ちの整理がついてきました。
結局、時間が一番の薬だったのかもしれません。
娘は、娘。
手帳があってもなくても、診断名があってもなくても、私が知っているこの子の「よさ」や「可愛さ」は、何も変わりません。
療育手帳を取得しても、デメリットなんて一つもありませんでした。
むしろ、支援の幅が広がり、気持ちが少し楽になった部分もあります。
行政や社会の「枠」に沿って動くことで、この子の選択肢が増えるなら、私はその“ラベル”を、利用できるものとして捉えていこうと思いました。
診断名がすべてじゃない。
ラベルがすべてじゃない。
この子自身を、ちゃんと見ていこう。
私はそうやって、少しずつ前に進もうとしていました。
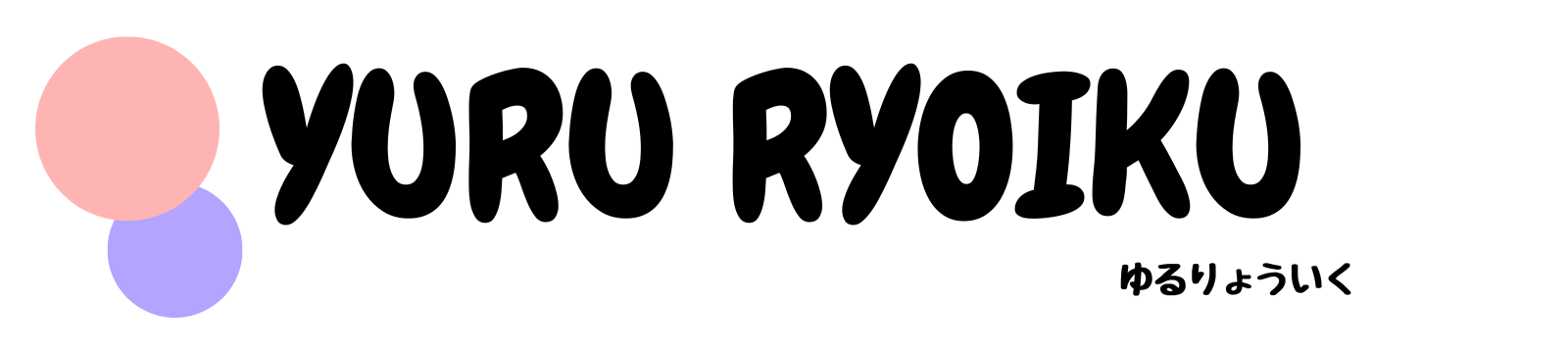
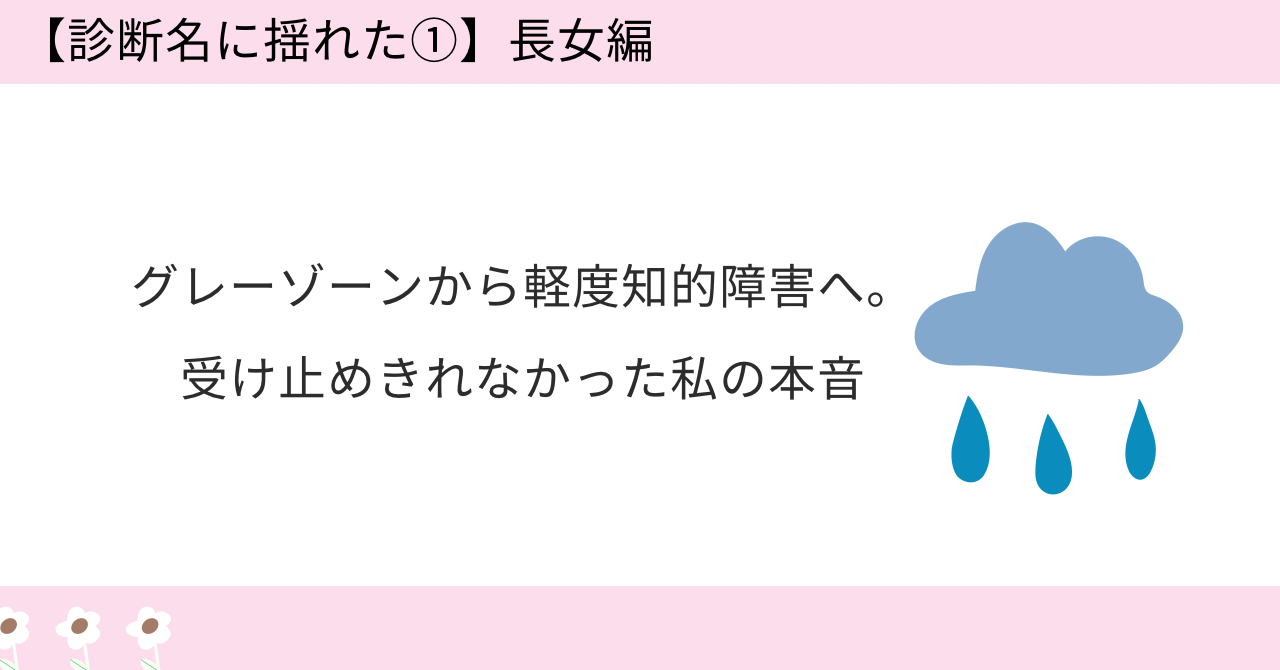





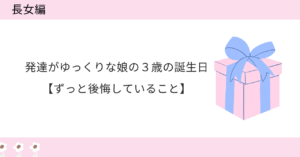

コメント