こんにちは、ゆるママです。
わが家の娘は、言葉の発達がとてもゆっくりでした。
1歳半健診では「まんま」「おいしい」など単語が出ていて様子見となったものの、その後は言葉がほとんど増えず、言えていた単語さえ出なくなる時期もありました。
発達検査では、2歳で「境界知能」、3歳で「軽度知的障害」と判定され、言葉の理解も遅れていて、特に言語面の課題を強く指摘されていました。
それでも家庭でできるサポートを続ける中で、少しずつ語彙が増え始め、言葉によるやりとりが増えていきました。
現在5歳の娘は、検査でも正常域とされ、定型の子たちと自然に会話できるようになっています。
 ゆるママ
ゆるママこの記事では、言葉が遅かった娘が家で行っていた「語彙を増やすための工夫」についてまとめています。
同じように「言葉がなかなか出ない…」と悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。
娘の言葉の発達を振り返ってみました
ここでは、娘の言葉の発達について、1歳半から5歳までを時系列で振り返ってみたいと思います。
■ 1歳半|「おいしい」「ねんね」など、意味のある言葉が少しだけ
1歳半ごろには、「おいしい」「ねんね」「まんま」などの単語がぽつぽつと出ていました。
発語数は多くありませんでしたが、意味のある言葉がしっかり出ていたので、1歳半健診では特に問題なしとされました。



上の子も言葉がゆっくりだったこともあり、「まぁ、そのうち話すでしょ」と、この時点ではあまり気にしていませんでした。
■ 2歳|言葉が増えない…むしろ減ってる?不安がふくらむ日々
ところが2歳を過ぎてから、新しい言葉がなかなか増えず…。
それどころか、以前は言えていた単語が出てこなくなることも。
たとえば、前は「わんわん」と言っていたのに、突然それを言わなくなったり…。
「また言えるようになるかな?」と様子を見ても、戻ってこない言葉もありました。



言葉って、増えるだけじゃなくて減ることもあるの?
減ってたら、いつまでたっても言葉が増えないじゃん……
と、毎日モヤモヤしていました。
■ 2歳4ヶ月|療育スタート。発語は「5語入れ替え制」状態
そんな中、2歳4ヶ月から療育に通い始めました。
通い始めた頃の娘の発語は、たったの5語ほど。
しかも、「前は言えていたけど、今は言わなくなった」というものも含まれていたので、実質“入れ替え制”のような状態。



ようやく10語に増えた!と思ったら、また別の言葉が出てこなくなっていて……。
「10語入れ替え制」みたいに、言葉が定着せず、増えていかない。
この時期は本当に苦しくて、



どうして言葉が増えないの?
と悩みすぎておかしくなりそうな日々でした。
■ 2歳8ヶ月|テレビ・動画をやめたら、言葉が爆発的に増えた!
そんな娘に転機が訪れたのは、テレビやタブレットを完全に排除したタイミングでした。
それまで家ではテレビをつけっぱなしにしていることが多く、動画にも夢中でした。
でも、「周りが見えていない」「集中が画面だけに向いている」と感じた私は、思い切ってテレビを処分。
タブレットや動画の存在自体も、娘にバレないように完全に“封印”しました。
すると、その直後から言葉が一気に増え始めたのです!



あれだけ出なかった単語がポンポン出るようになり、気づけば100語近くまで一気に増えた感覚がありました。
やはり、目や耳を向ける「対象」が変わったことで、周囲の言葉ややりとりに目が向くようになったのかもしれません。
■ 3歳|知っているのに出ない言葉。語彙のアンバランスが目立ち始める
3歳になっても、語彙の伸びはゆっくりでした。
2歳8ヶ月で言葉の爆発期が来ていましたが、このころは停滞期でした。
見れば理解しているはずなのに、なかなか言葉として出てこないものが多く、とくに「野菜の名前」が苦手でした。
たとえば、
- キャベツ
- かぼちゃ
- しいたけ(→すべて「きのこ」で済ませる)
など、よく見ているはずの食材でも、うまく名前が出てこないことがよくありました。
会話のほとんどはまだ単語中心で、「〇〇 たべた」「ママ きた」などの2語文も安定せず。
動物の名前も「いぬ」ではなく「ワンワン」、「ねこ」ではなく「にゃんにゃん」といった赤ちゃん言葉が中心でした。
「わかってるのに、なんで出てこないのかな…?」
そんなもどかしさを感じつつも、少しずつでも言葉が出てくることを信じて、家庭での語彙サポートを続けていました。
■ 3歳半|2語文が安定。でも、聞き取りづらさは続く
3歳半ごろになると、ようやく2語文が安定して出るようになってきました。
「ママ きた」「パン たべたい」など、簡単なやり取りはスムーズに。
ただし、発音がとても不明瞭で、何を言っているのか聞き取るのが本当に大変でした。



親の私でも、「え?何て言ったの?」と何度も聞き返すことが多く、やり取りに苦労する日々でした。
■ 4歳|言葉の中身が少しずつ豊かに。語彙の引き出しにはムラも
4歳になると、まだ不明瞭な部分はありつつも、何を言いたいのかは伝わるレベルに。
3語文や少し複雑な会話も増え、経験したことを話す力も少しずつ育ってきました。
たとえば、「きょう、せんせいと えほん よんだ」と、過去の出来事を話すことができるように。
ただ、語彙の引き出しにはムラがあり、知っているはずの言葉がなぜか出てこない場面も。
キャベツの名前がどうしても出てこなかったり、「あれ」とか「これ」で済ませたり…。
語彙そのものというよりも、適切な言葉を引き出して使う力がまだ弱い印象でした。
■ 5歳|日常会話には困らない。言葉で伝える力も成長中
5歳になった今では、日常のやり取りにはほとんど困ることはなくなりました。
幼稚園での出来事も、自分の言葉でしっかり説明してくれるように。
ただし、語彙の数や文の構造は、まだ同年代と比べるとやや幼い印象です。
でも、本人が言葉で困っている様子はなく、伝えたいことをきちんと話せている実感があります。
語彙を増やすために家で工夫したこと
娘の語彙を増やすために、家庭でいろいろな工夫をしてきました。ここでは特に効果を感じたものを紹介します。
【2歳】自転車でのおしゃべりタイム|移動時間も語彙のチャンスに
日々の移動中、自転車の前に娘を乗せている時間は、私にとって“語彙シャワー”のような時間でした。



まだ言葉が少なかった頃から、とにかくたくさん話しかけるようにしていました。
自転車の前に乗っていると、娘の耳がすぐそばにあるので、家の中よりも聞き取りやすい環境だったと思います。
「右にまがりまーす」「公園が見えてきたね」「あれは救急車だよ」「今日は雲が多いね」など、思いついたことをなんでも実況中継。
とくに印象に残っているのは、トンネルを通るときのやりとりです。
毎回、「トンネルに入りまーす。真っ暗だね〜、夜みたいだね」と声をかけていました。
2歳の頃の娘は、聞いているのかいないのか分からないほど無反応で、返事も一切なし。
でも、ある日3歳になった頃、自転車でトンネルに差し掛かると、娘が突然、
「トンネルはいりまーす。まっくら〜!」
と、まさかの完コピ。



やっぱりちゃんと聞いてくれてたんだ、と胸がじーんとしました。
言葉が出ていなくても、耳や心にはちゃんと届いている。
そのことを実感した、忘れられない出来事です。
【2歳】絵本・図鑑|“喋る”ための準備期間に
絵本や図鑑は、言葉を育てるうえで欠かせない“基本のツール”として、ずっと取り入れてきました。
正直なところ、絵本を読んだからといって、すぐに喋るようになったわけではありません。
でも、



「知っている言葉をとにかく増やす」ことを目標に、毎日続けてきました。
語彙がまだ口から出てこなくても、頭の中にしっかり蓄積されている感覚はあって、実際に言葉が出始めたときには「あ、この子、実はいっぱい覚えてたんだな」と思う場面が何度もありました。
「どうせ意味がないんじゃないか」「まだ理解していないかも」と感じる日もありましたが、それでも毎日少しずつ絵本や図鑑に触れさせるようにしていました。
なので、



もし「見せても意味がない」と感じている方がいたら、「耳や目から入った言葉は、いつか出てくるかもしれない」くらいの緩い気持ちで、続けてみてほしいです。
図鑑は、イラストではなく、動物や野菜の実物の写真が載っているものの方が、娘にはわかりやすいかなぁと思い、
こちらのものを使っていました。
有名な絵本ですが、だるまさんシリーズは、娘も大好きでした。
動きの真似で遊べるので、言葉が出る前でも、読むと喜んでくれました。
この本も、音で楽しめる本なので、子どもが興味を持ちやすいと思います。
こちらの記事で、最近おすすめの図鑑について、書いています。


【3歳】公文教室に通って刺激になったこと
言葉がなかなか増えない娘に、少しでも“言葉に触れる機会”を作ってあげたくて、公文に通わせ始めました。
最初は、「本当に3歳で公文なんてできるのかな」と不安もありましたが、ひらがなと絵を見ながら「いぬ」「ひこうき」「りんご」と読む練習をすることで、毎日の音読と語彙の積み重ねが自然とできるようになりました。
家での宿題もあり、毎日10枚のプリントに取り組む中で、言葉を声に出す機会がぐんと増えました。
喋らない娘にとっては、毎日声を出す“口の筋トレのようなものだったかもしれません。
正直、最初の頃は、娘が頑張って発音しても、何を言っているのか分からないくらいちゃんとした音にはなっていませんでした。
それでも、



毎日取り組むと、だんだん上手になっているのが、わかるんです。
1年が経つころには、ちゃんとした言葉になっていました。
【4歳】自宅カラオケで楽しく発音練習
歌が大好きな娘にとって、歌は“遊び”でありながら、歌を通じた自然な言葉のアウトプットでもありました。
家では、Nintendo Switchの「カラオケJOYSOUND」を使ったカラオケタイムが定番に。



リズムに乗って繰り返し声を出すことで、発音の練習にもなり、何より本人が楽しめるのがポイントでした。
好きな歌を通して言葉に触れる時間は、無理なく、でもしっかりと語彙力アップにつながっていたように思います。
我が家は、スイッチを持っていなかったのですが、カラオケを家でしたい!と思い、思い切って購入しました。



私のストレス発散にもなっています。
テレビ・タブレット断ちの影響
【2歳】動画大好き娘に“見せない選択”辞めた理由
娘は、小さい頃から動画が大好きでした。
特に2歳ごろは、タブレットやテレビに過集中していて、動画を見ている間はまるで“周りが存在しない”かのよう。
こちらが話しかけても全然耳に入っておらず、視線も反応も画面にくぎづけでした。
テレビを消すと泣き叫ぶこともあり、正直、私も「もういいや…」と流してしまいそうになることも。
でも、そんなある日、家族がコロナにかかり、1週間の自宅待機となりました。



このままでは、その間ずっと動画漬けになる…。
そう思った私は、意を決して*テレビを2階に隠しました。
タブレットも封印。
家の中に映像機器が“存在しないことにする”という荒療治でした。
実際の変化
娘が寝ている間にこっそりテレビを隠してみました。
翌朝、怒ったり泣いたりするかと心配していたのですが、まったく気づかない様子で、穏やかな朝を迎えました。
まるでテレビがなくなったことに気づいていないかのように、あっさりとテレビ離れができました。
テレビをなくしてから数日で、驚くほど良い変化が見られました。デメリットはまったくなく、メリットばかりを感じています。
- 目が合うようになった
- 音に反応して振り向くようになった
- おもちゃで遊ぶ時間が増えた
- 絵本に興味を持つようになった
そして少しずつ言葉のやり取りにも変化が現れ、2歳8ヶ月の言葉の爆発期の大きなきっかけになったと思います。



「テレビの見せすぎは良くない」とよく言われますが、娘にとってはまさにその通りでした。
【5歳】今は週1〜2回に戻している理由
2〜3歳のころは、テレビも動画も完全にやめていました。
今もテレビは家に置いていないままですが、4歳くらいから少しずつ、タブレットや簡易シアターを使って動画を見せるようになりました。
というのも、少しずつ約束が守れるようになってきたから。
今(5歳)は、週に1〜2回くらい、動画を楽しむスタイルです。
時間を細かく決めているわけではないけれど、だいたい1時間半くらいまでにしています。
スムーズにやめられるように、出かける前やごはんの前、お風呂の前など、切り替えやすいタイミングで見せるようにしています。
見るのは、「プリキュア」や「ドラえもん」など、幼稚園のお友達と話題にしやすい番組が多いです。
テレビをやめたあの時期を境に、娘の“ことば”と“人への興味”がぐんと戻ってきたように感じています。



あのテレビ断ちが、語彙の芽が育ち始めた原点だったんだろうな、と今は思っています。
ことばは、ゆっくりでもちゃんと育つ。あの頃の私へ伝えたいこと
言葉の発達が遅くて、不安でいっぱいだったあの頃の私。
「どうして話さないの?」「これからちゃんと伸びていくのかな…?」
そんな気持ちで、毎日ネットを検索しては、他の子と比べて落ち込む日々でした。
でも今振り返ると、あの頃の小さな積み重ねが、娘の語彙を少しずつ育ててくれていたんだと思います。
時間はかかっても、言葉はちゃんと届いて、根づいて、いつか芽を出してくれる。
この記事では“言葉”にフォーカスして書いてきましたが、実は、理解力の伸びにも大きな変化がありました。
娘は「軽度知的障害」と診断されたあと、家庭での関わりを工夫しながら学びを続けた結果、2年間でIQが24も伸び、現在は正常範囲とされています。
その背景には、言葉だけでなく“理解力”や“考える力”を育てる日々の取り組みがありました。
理解力・知能の成長については、こちらの記事でくわしくご紹介しています。
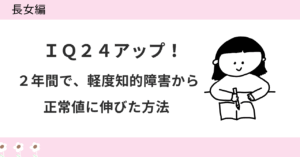
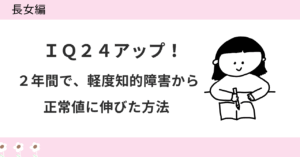
「ことば」も「理解力」も、ゆっくりでも、子どもはちゃんと育っていきます。
この記録が、同じように悩んでいる誰かの心を、少しでも支えられたら嬉しいです。
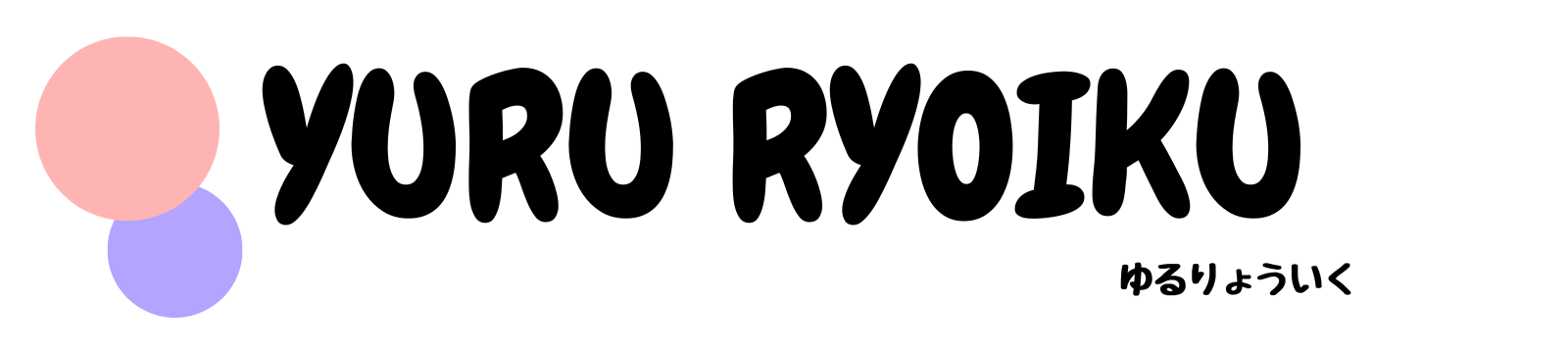









コメント