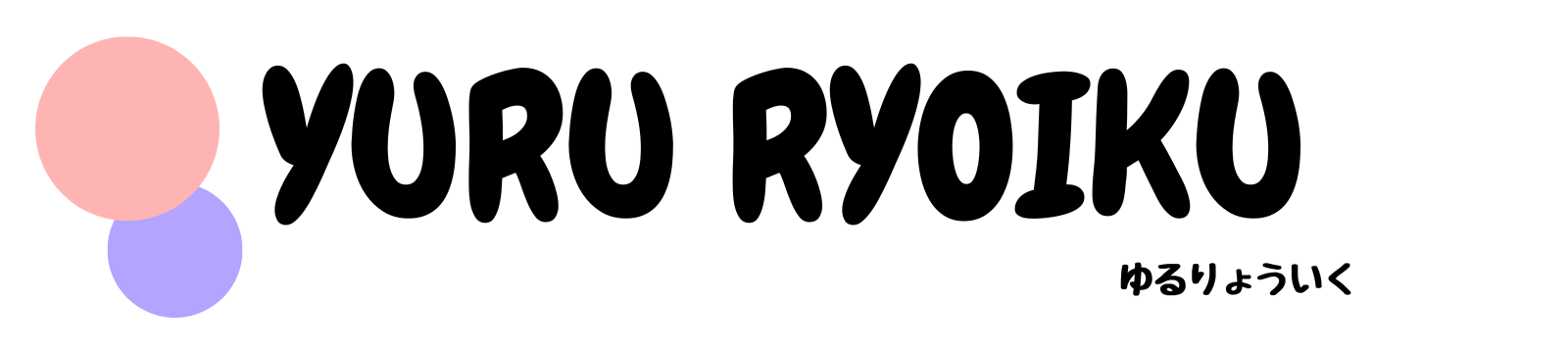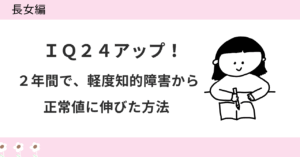「このまま療育を続けていていいのかな?」
子どもの発達に課題が見つかったとき、多くの家庭が「療育」を選択します。
けれど、一度通い始めると、次に訪れるのは「やめどきがわからない」という迷いではないでしょうか。
この記事では、わが家の子どもたちが「療育を卒業するまでのリアルなプロセス」をたどりながら、「やめどき」のサインについて実体験をもとに綴っていきます。
]
療育に追われる日々の始まり
朝も午後も療育、兄妹をバトンのように送り出す日々
長男・長女ともに、発達検査の結果は「境界知能」で、2人とも言葉がゆっくりでした。
そのため、2人そろって療育を始めることになりました。
当時、幼稚園に通っていた長男は週2回、未就園児だった長女は週4回の個別療育に通っていました。
午前は長女、午後は長男というスケジュールで、私はまるでバトンを渡すように、子どもたちを送り出していた日々でした。
「今が踏ん張りどき」と自分に言い聞かせていた
 ゆるママ
ゆるママ長男にもっと集団で過ごす練習をさせてやりたい。
そう思って空き待ちをしていた施設に、ようやく通えるようになり、長男は集団、長女は個別という新しいリズムが始まりました。
雨の日も、風の日も、前と後ろに子どもを乗せて自転車をこぎ続けました。
私の中には常に、「今が踏ん張りどき。将来につながる」と自分を奮い立たせる思いがありました。
「療育が日常」になることの違和感
幼稚園を休んでまで通う療育。私の中に芽生えた瞬間
その後、長女が3歳の誕生日を迎え、満3歳児クラスの幼稚園に入園しました。
兄妹ともに週2日ずつ療育に通い、空きがあれば追加で受けるという生活を続けていました。
長女が週4日通っていた頃に比べると、少しだけ気持ちに余裕が生まれたようにも感じていました。
そんな中、長女はすでに幼稚園に通っていたにもかかわらず、2歳のときに順番予約をしていた療育センターの親子療育にも参加することになりました。
毎週決まった曜日、幼稚園に通う長男を見送ってから、本来なら一緒に登園するはずの長女を連れて、療育に向かう。
週1日とはいえ、



長女が楽しんで通っている幼稚園を休んでまで、療育に行く意味があるのだろうか?
と違和感を抱いていました。
心のどこかでそう思いながらも、療育センターや幼稚園からの強い勧めもあり、通所を続けることに決めました。
「療育ありき」で回る生活に疲れていた
いつの間にか、我が家の生活は「療育ありき」で回るようになっていました。
朝は誰がどこへ行くのかを確認するところから始まり、スケジュール帳は療育の予定でいっぱい。
そんな生活が続く中で、私自身がすり減っていたのかもしれません。
「このままでいいのかな?」と思い始めた瞬間
子どもたちの成長とともに感じた違和感
日々の療育に追われながらも、子どもたちは少しずつ成長していきました。
その成長が見えてきた頃、私は、ふと



このままでいいのだろうか…?
と立ち止まるようになりました。
優しい空間が、外の世界を遠ざけているように思えた
グレーゾーンの長男、軽度知的障害と診断されていた長女。
療育が必要なことはわかっていました。
それでも、



この優しく整えられた空間が、いつか子どもたちの自立を妨げてしまうのでは?
という思いが心に浮かび始めていました。
「もしかして、この子たち、大丈夫かもしれない」と思えた日
公文との出会いがもたらした転機
長男が年中、長女が満3歳クラスの終わりを迎える頃、公文を始めることにしました。
電話で「発達がゆっくりなんですが……」と伝えたとき、先生の「大丈夫ですよ」の一言に、張りつめていた心がほどけました。
定型の子たちと並んで学ぶ姿に見た“兆し”
公文に通い始めた2人は、家でも教室でも、他の子と同じように宿題に取り組むようになりました。



もしかしたら、この子たち、大丈夫なのかもしれない
その感覚は、私にとって大きな希望でした。
長男が療育を卒業した日
習い事で見せる「生き生きとした姿」
長男は公文に加えて、「やってみたい」と自分で希望したスイミングを始めました。
習い事では、幼稚園とはまた違った生き生きとした表情を見せてくれるようになりました。
卒園と同時に迎えた、静かな「卒・療育」
そんな中、長男は幼稚園の卒園と同時に、療育も卒業することになりました。
年少の終わりから、2年ちょっと通いました。
本人はあっさりとしていましたが、私は胸の中で「よくここまで来たね」と、小さく拍手を送っていました。
長女の“卒・療育”は、3度目の発達検査で
検査結果と、私の中にあった確信
長女が年中の秋、3度目の発達検査を受けた結果、「IQは正常の範囲です」と言われました。
すでに私の中では、



この子にはもう療育は必要ないのかもしれない。
と思い始めていたため、その結果は静かな後押しになりました。
「この子はもう大丈夫」と思えた理由
数字だけ見れば、療育を続けるという選択肢もあったかもしれません。
正常範囲とはいえ、IQは100に届いていませんでした。
けれど、私は「やめる」という決断をしました。
幼稚園でも、習い事でも、のびのびと過ごす姿を見て、



もうこの子は自分の力で進んでいける!
と思えたからです。
濃くて長い、3年間の療育を振り返って
長女は、2歳から5歳まで、およそ3年間にわたって療育に通いました。
振り返れば、それはもっと長く感じるほど、濃い時間でした。



あんなに子どもたちのことで悩んだ日々は、もう二度と来ないのではないか…
と思うほど。
毎日のように「これでいいのか」「ほかにできることはないのか」と悩み続けた3年間。
今ももちろん迷うことはあるけれど、あの頃とは少し違います。
どこか、少しだけ肩の荷が下りたような気がしています。
それは、子どもたちが成長したからなのか、私自身が少し強くなれたからなのか…。
きっと、そのどちらもなのだと思います。
療育の終わりに思うこと。焦らなくても、終わりは来る
あの頃の自分に、伝えてあげたい言葉
朝から晩まで療育に追われていた日々は、今思えば必死すぎて、余裕がほとんどありませんでした。
それでも、その時期があったからこそ、今があります。
子どもも親も、想像以上に強かった



療育を「卒業する日」が来るなんて、始めたばかりの頃には思ってもいませんでした。
でも、ちゃんとそのときはやってきました。
完璧になったわけじゃないけれど、私は確かに「この子たちは、もう自分の足で歩いていける」と思えたのです。
おわりに今、療育を続けるべきか迷っているあなたへ
「やめどき」は、迷いとともにやってくる
療育をやめる。そう決めることには、想像以上の勇気がいります。
「本当にもう大丈夫だろうか」
「やめてしまって、困ることがあったらどうしよう」
そう思うのは当然です。私も、何度も立ち止まっては迷いました。
終わりを決めるのは、はじまり以上に怖く、不安がつきまといます。
それでも、子どもと向き合いながら過ごす日々のなかで、少しずつ見えてくる変化があります。
誰かに決めてもらうのではなく、自分の中でじわりと浮かび上がってくる「もう、大丈夫かもしれない」という感覚。
それが、わが家にとっての“やめどき”のサインでした。
焦らず、その子の歩みに寄り添って
その小さな感覚を信じて、一歩踏み出してみてください。
怖さや不安を抱えたままでも、大丈夫。
焦らなくても、ちゃんと「終わり」はやってきます。
それは、「もう療育が必要ない」と思えるくらい、あなたのお子さんが育ってきた証です。
いつか、「ああ、あのとき頑張ってよかったな」と思える日が、きっと来ます。