幼稚園での面談で「発達の遅れ」を指摘された日
少しゆっくりだとは思っていた
長男が4歳になったばかりの幼稚園での面談。
発達ゆっくりを指摘され、療育センターを勧められました。
普通よりちょっと遅いとは思っていました
でも、1歳半健診とか、3歳健診とか、そういう区切りの検査は、一応クリアしていたし、発達が遅いことを相談しても、「お母さん、大丈夫ですよ。男の子は、ゆっくりな子もいるから」と言われ続けていました。
言葉も喋っていたから、まさか今さら幼稚園の先生にそんなことを言われるとは、思いもしませんでした。
担任の先生の言葉にショックを受けた
担任の先生に、息子ができないことをつらつら言われ、息子の悪口を聞かされている気分で、泣きたくなりました。
正直、何を言われたのか記憶が欠落しているくらい、ショックでした。
同時に、先生に指摘された長男よりも、更にゆっくり発達の2歳の長女のことも気になりました。
 ゆるママ
ゆるママ先生、長男よりもかなり言葉が遅い下の子がいるんですけど(心の声)
4歳の長男と2歳の長女を連れての面談だったから、面談中は、なんとか泣くのは耐えたけれど、2人を乗せて自転車で帰りながら、涙があふれてきました。
怒りと悲しみとショックと、いろんな感情が湧き上がって、頭の中も心もぐちゃぐちゃで苦しかったです。
夫にどう伝えようか。
息子を否定されたような言葉を、自分の口から出したくありませんでした。
でも話さないわけにはいきませんでした。
夫に話すと、夫は先生に怒っていました。
母に電話しても、同じように怒ってくれました。
でも、話しているうちに、私はどんどん冷静になっていきました。
「普通の育児」が少しずつ揺らぎ始めた瞬間



確かに発達はゆっくりだった。でも、ゆっくり進んでるだけ。普通の範囲だと思い込んでいた。
けれど、そうじゃないかもしれない。
そう認めることで、ようやく私は療育センターに電話をかける決心がつきました。
療育センターでの発達検査で兄妹2人とも「境界知能」と診断された
長男IQ82、長女DQ76という現実
療育センターに電話して、予約、そして発達検査を受けに行きました。
「何かしないと、この子は取り残されてしまう」焦りと不安でいっぱいでした。
結果は、
長男(4歳):IQ82、10ヶ月の遅れ
長女(2歳):DQ76、明らかに平均から離れている
2人とも、境界知能。
正常範囲には届いていませんでした。
「普通じゃない」という烙印を押された気がした
「普通じゃない」という烙印を押されたような気がしました。



母親として、私は何をすればいいのか?これからこの子たちはどうなるのか?
その問いが、心の中でぐるぐると渦を巻きました。
目の前の先生は、あくまで事務的に、淡々と説明を続けていました。
数値、発達の遅れ──どれもまるで、他人事のようでした。
「境界知能」「グレーゾーン」という言葉の重さ
私はその場で言葉を失っていたけれど、頭の中ではずっと叫んでいました。



正常じゃないんだよね⁉︎
なんでそんなに平然と話せるの?
心が追いつけない。現実を受け入れる準備なんて、できていませんでした。
「境界知能」「グレーゾーン」って、なに?
その言葉が示す現実の重みを、私はまだちゃんと理解できていませんでした。
ただただ、目の前が真っ白で、胸の奥がギュッと痛んでいた。
妹は療育対象、兄は「様子見」…支援の壁
なぜ兄だけが療育対象外なの?
2歳の長女には「早期療育が有効です」として、定期的な通所を勧められました。
まだ就園前で、療育の受け皿があるから、という説明もありました。
なるほど、そうなのか……と、納得しかけた矢先。
長男に関しては、「幼稚園に通っているし、今すぐ療育は必要ないでしょう」と言われました。
困っていない”の基準とは?
「困り感が出たら、また来てください」
その言葉を聞いた瞬間は、「は?」と何を言われたのかわかりませんでした。
あんなに幼稚園の先生に「気になります」と言われたのに。
こっちはショックでボロボロになったのに。
“困り感”って、じゃあ今のこれは“困ってない”ってことなの?
引っかかっていた、「グレーゾーン」という言葉。
診断としては「境界知能」、正常ではないけれど、障害とも言い切れない。だから支援の対象にはならない。
そんな“扱いにくさ”が、そこにはありました。
「どちらでもない子ども」がこぼれ落ちる支援
中途半端だから、支援は受けられない。でも、普通でもない。
どちらでもない子ども。どこにも居場所がない。
長女には「通ってください」と言われ、長男には「様子を見ましょう」と言われる。
年齢の差なのか、それとも「軽度知的障害よりの数値」という判定が影響したのか。



兄妹でこんなにも対応が違うことに、私は強い違和感と不安を覚えました。
たった2歳差なのに、妹には「すぐに支援を」と言われ、兄には「まだ様子を見ましょう」。
どちらも“境界知能”と結果が出たのに、妹は療育の対象で、兄は対象外。
じゃあ、長男はどうしたらいいの?
本人がもっと困らないと、支援は受けられないの?
その「困っている」って、誰がどう判断するのだろう?
幼稚園の先生は「このままだと心配です」と言っていたのに、それは“困っている”に入らないのだろうか?
あの日の面談から、私はずっと混乱していました。
診断名がつかないから支援がない。でも、診断名がついたら、それはそれでまた怖い。
でも、このまま何もしなければ、きっと追いつけないと思いました。
実際、幼稚園では、「話を聞いていない」「工作の工程が理解できない」と、具体的にできないことを指摘されていました。
なのに、専門機関では「様子を見ましょう」で終わってしまいます。
このギャップは、何?どっちを信じればいいの?
「支援が必要な子」には見えないけれど、実際には困っている。
「困っているように見えない」という理由で、支援の対象から外れる。
でも、私から見れば、確実に“助け”は必要でした。
何も変わらない日常。
それでも、少しずつ広がっていく周囲の子との違い。その現実に、私は追いつけず、ただ焦るばかりでした。
「何もしない怖さ」に背中を押されて
グレーゾーンの子どもは、見えにくいからこそ放置されやすい。明確な診断名がつかないことで、支援の枠から外される。
「様子を見ましょう」「そのうち伸びますよ」
そんな言葉の裏にある、「何もしない」という選択。
親にしか見えない違和感
でも、親から見たらわかります。
小さなつまずき、日常の中にある違和感。「できない」わけではない。でも「同じようにできない」。
それが、どれだけ本人を苦しめるか。
“支援が必要なほどではない”という理由で、何もしてもらえない。
それが、ものすごく怖かったのです。
このままでは後悔するかもしれない



このまま何もせずにいたら、「もっと早く動いていれば…」と後悔する未来が来る気がしました。
だから、私が動かなきゃいけない。
まだはっきりと“困っている”とは言えない今だからこそ、困る前に動くことが、親にしかできないことだと思いました。
この子の育てにくさを、「気のせい」や「親の心配性」で済ませてしまったら、この先、誰が本気で向き合ってくれるのだろうか?
幼稚園? 医療機関? 福祉?ううん、たぶん、誰も動かない。
私だけが、この子の未来を守れる。その思いが、私を突き動かしました。
誰にも背中を押されていないけど、もう立ち止まるわけにはいきませんでした。
民間療育を探し、ようやく見えた選択肢
検索、電話、見学…
すぐにインターネットで「民間 療育 ○○市」と検索しました。
口コミを読んで、電話して、空き状況を聞いて、長男と長女を自転車に乗せて、見学に行きました。
- 民間療育って何?
- どこがいいの?
- 何を基準に選べばいいの?
- そもそも空きはあるの?
わからないことばかりだったけれど、わからないなりに調べるしかありませんでした。
他のママと違う育児をしているという孤独
周りのママ友は、「そろそろスイミング行かせようかな〜」「英語教室通い始めたよ〜」なんて話をしています。
本当なら、私もその輪の中にいるはずでした。
年少になった長男に、習い事でもさせようかと考えていた時期でした。
なのに今の私は、



「境界知能の子が2人いるんですが、療育って受けられますか?」
と、問い合わせています。
他の子とは、違う、現実。親になって初めて、「普通の育児」の外にいることを痛感しました。
公的支援からあふれた親のリアル
幸い、民間の療育施設はすぐに見つかりました。
見学したその場で、通所の目処も立ち、本当にありがたいことだったと思います。
でも、同時に、



どうして療育センターは、こういう選択肢を教えてくれなかったんだろう?
と思いました。
私のように、何も知らずに立ち尽くす親は、きっと他にもいるはずです。
育児が「療育」になった私の日常
発達を伸ばすことが最優先の毎日
ある日、ふと気づきました。



私、毎日「どうすれば発達が伸びるか」ばかり考えている。
それはもう、「子育て」というより、「療育」になっていました。
「可愛いね」「面白いね」「大きくなったね」って、ただのびのびと見守る育児ではなくて、どこか常に「間に合うように急がせる」毎日になっていました。
比べてしまう心と、焦りとの葛藤
本当は、他の子と比べちゃいけないってわかっています。
わかっているけれど、どうしても比べてしまうのです。



あの子は、もうお話が上手。
あの子達は、先生の話をちゃんと聞ける。
うちの子は、まだここなのに。
比べたって意味がない。そう思い直しては、また気持ちが揺れるのです。
それでも私は、笑うようにしていました。
でも、心のどこかにはいつも“焦り”が住みついていました。
私だけ、違う場所で子育てをしているように感じていました。
「普通」とは違う幸せのかたち
初めての「ママ」、ひらがなが書けた日
長女が、はじめて「ママ」と呼んでくれたとき。
長男が、自分の名前をひらがなで書けるようになったとき。
それは、世間ではきっと「当たり前」の出来事かもしれません。
でも、私にとっては、涙が出るほど、嬉しく感じました。
「小さな一歩」が大きな喜びに変わる
ほんの小さな一歩が、心の奥を震わせるほどの喜びになります。
「普通」に育っていたら、きっと見逃してしまっていたような、そんなささやかな成長が、私は、それを何倍にも大きく感じることができます。
たしかに、私たちの育児は「普通」とは少し違ってしまいました。
でも、だからといって、すべてが苦しいわけじゃありません。
あのとき、泣きながらでも自分で動いた一歩があったから、今のこの子たちがいて、そして私自身が、壊れずにここに立っていられます。
「普通」に近づけるための育児。
それが本当に正しい道なのかは、今でもわかりません。
でも、私はこの子たちのために、私自身のためにやるしかないのです。
「普通の育児」じゃなくても、大丈夫。
発達の遅れを指摘されたあの日から、私の子育ては「普通」ではいられなくなりました。
境界知能、グレーゾーン。
はっきりしない言葉に、不安と焦りだけが膨らんで、何を信じていいのか分からなくなった日もありました。
でも、迷いながらも動いたことで、少しずつ見えてきたことがあります。
「普通の育児」ではないからこそ気づける、小さな成長の喜び。
誰にも気づかれない一歩が、親子にとっては大きな意味を持つということ。
子どもの発達がゆっくりでも、グレーゾーンと言われても、それは「できない」ではなく、「その子のペース」で進んでいるということ。
療育に迷いながらも、手探りで選んだこの道が、きっとこの子たちの未来につながっていく。
今は、そう信じています。
「普通じゃない」育児の中にある、確かな愛と希望を、私はこれからも大切にしていきたいです。
▼発達の不安を抱えていた当時、3歳の誕生日をどう迎えたのか。私自身の揺れる気持ちと、その日の記録をこちらにまとめています。
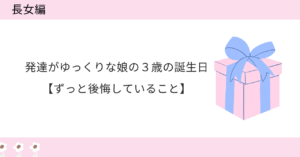
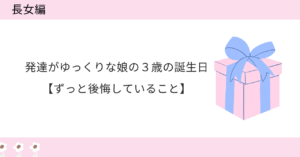
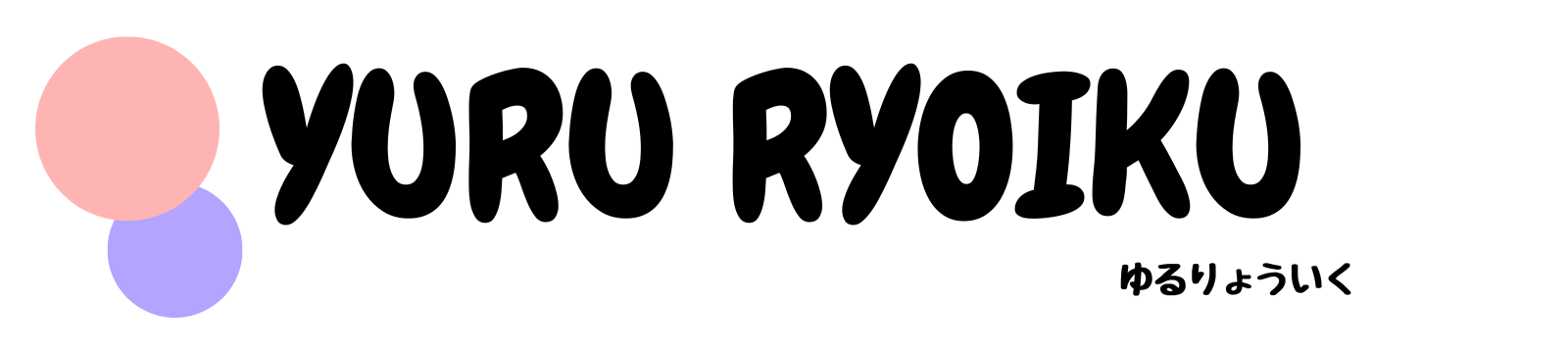










コメント