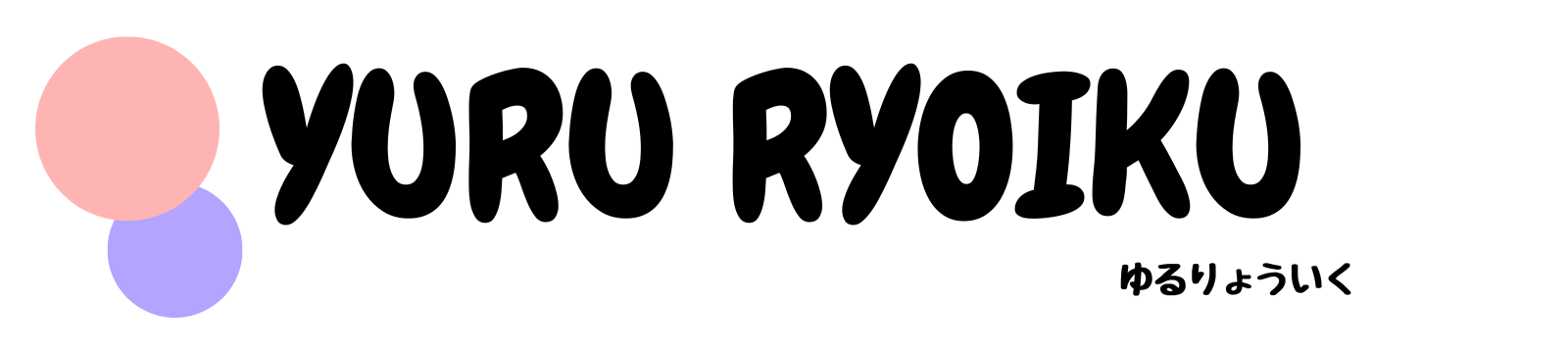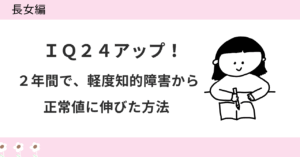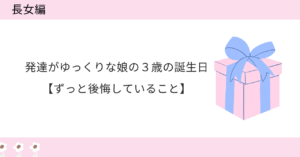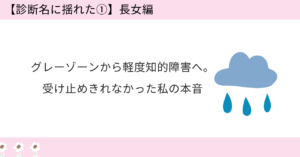こんにちは、ゆるママです。
うちの長男は、いわゆる「発達グレー」と言われるタイプ。
でも、発達検査は4歳のときに受けた、たった1回だけ。
その後も再検査はしていませんし、就学相談もせずに、小学校の進路を決めました。
 ゆるママ
ゆるママもっと検査を受けるべきだった?通常級でこのまま大丈夫?
そんな迷いと不安がずっとありました。
それでも、私があえて“見守る”選択をしてきた理由と、当時の葛藤について、同じような立場で悩む方の参考になればと思い、記録として残しておきます。
発達検査を受けたのはたった1回。それでも“グレー”と分かった
最初の発達検査は年少の冬
幼稚園年少のとき、担任の先生からこう言われました。
「言葉がゆっくりで、会話がうまく続きません。指示もなかなか通りません」
心配になり、療育センターで発達検査を受けたのが4歳の冬。
結果はIQ80台前半。いわゆる「境界域」に当たる数値でした。
軽度知的障害には当てはまらない 。
かといって「正常範囲」にも届かない。
このグレーの結果をどう受け止めるか、正直かなり悩みました。
「様子見で大丈夫」と言われても、不安は消えなかった
療育は「必要なし」と言われたけれど
発達検査のあと、療育センターからはこう伝えられました。
「今すぐ療育が必要な状態ではありません。様子を見ていいと思います」
でも私は、「何もしない」ことが不安でした。
それで、民間の療育施設を探し、年少の終わりから年長まで通うことにしました。
再検査をしなかった3つの理由
① 数値が“グレー”から大きく動く可能性が低いと感じた
初回の発達検査では、正常範囲にあと数ポイント届かず、軽度知的にも入らない数値。
正直、再検査をしてもまた“グレー”か、正常にギリギリ入るかのどちらかになる気がしていました。
どちらにしても、支援や環境が大きく変わるわけではない。
そう思って、再検査は見送りました。
② 本人が療育センターを苦手にしていた
当時、療育センターへの通院をあまり好まず、行きたがらない様子が見られました。
苦手な場所で無理に検査を受けさせても、親子ともにストレスが増えるだけだと思い、受けないことにしました。
③ 数値が下がる可能性があるのが、何より怖かった
正直、「正常でした」と言われたら安心できるという思いもありました。
でも、万が一下がってしまっても、支援がつくわけではなく、「ただ落ち込むだけ」という結果になるのが一番つらい。
だったら、現状維持でいい。
その判断が、今のわが家には合っていると思いました。
周囲からの目が気になる気持ちもあった
「検査を受けないなんて、現実から目を背けてるだけじゃないの?」
「親として、もっとしっかり向き合うべきじゃないの?」
そんな声をかけられたわけではありませんが、自分の中に、そう責めてくる誰かの声がありました。
だけど、誰よりも子どもの姿を見てきたのは親の私。
長男の様子を見ながら、「今は受けなくていい」と判断したことに、今は後悔はありません。
兄妹でも対応は違う。正解は子どもによって違う
長男は、発達検査を4歳のときに1度受けただけですが、妹(長女)は3回も検査を受けています。
同じ家庭で育っていても、子どもそれぞれに必要な支援や対応はまったく違う。
「1度しか受けてないのはおかしい」「3回も受けるなんて」と外から言われても、家庭の事情や子どもの特性を知らない人には判断できません。
受けても、受けなくてもいい。
何度受けても、1回だけでも、それは親の判断で決めていいと思っています。
グレーゾーンの子と向き合う日々は、正解のない選択の連続
長男は現在、小学2年生。
通常級で頑張っていますが、発達面で気になることがまったくないわけではありません。
でも、「今どうか」だけで判断するのではなく、「今、何を選んだら、親子で前向きに進めるか」を大事にしています。
グレーゾーンの子育てには、明確な正解がありません。
だからこそ、親が迷いながらも「これが我が家のベストだ」と思える判断を重ねていくしかないのだと、今は感じています。